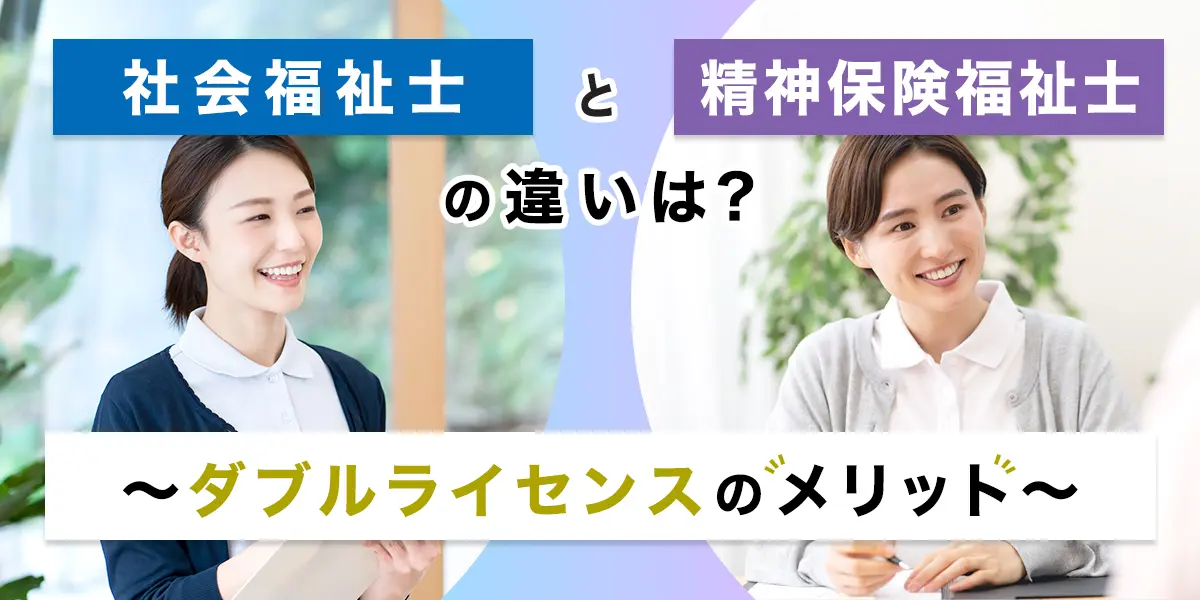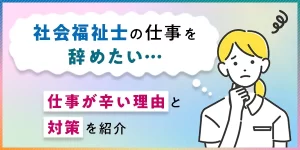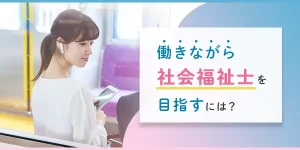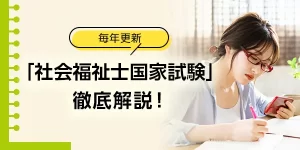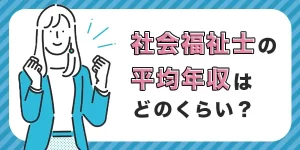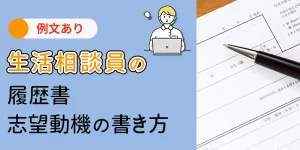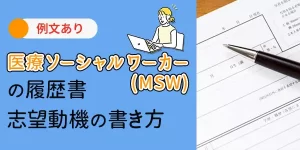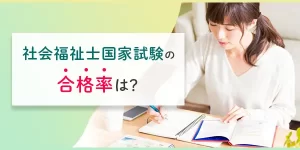社会福祉士と精神保健福祉士の明確な違いを比較し、あなたに最適なキャリアプランを解説します。
「どちらを目指すべき?」と悩んでいる方へ、支援対象や仕事内容の違いから、両資格を持つ「ダブルライセンス」のメリット、共通科目免除を活かした効率的な資格取得ルートまで紹介。
理想のキャリアを考える第一歩としてご活用ください。
目次
社会福祉士と精神保健福祉士の5つの違い【一覧表で比較】
社会福祉士と精神保健福祉士は以下のような違いがあります。
| 項目 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|
| 支援対象 | 高齢者、児童、障がい者、生活困窮者など生活に課題を抱える幅広い対象 | 精神障がい者とそのご家族が中心 |
| 主な仕事内容 | 適切な福祉サービスの利用援助、施設や公的機関・病院などでの相談支援全般 | 精神科病院の入院患者の退院支援や社会復帰支援、地域で暮らす精神障がい者の生活の支援、企業でのメンタルヘルスなど |
| 活躍の場 | 福祉施設や公的機関・病院など幅広い福祉現場 | 精神科病院や障がい福祉サービス事業所、公的機関、企業など |
| 資格取得ルート | 福祉系大学または養成施設の修了+国家試験 | 福祉系大学または養成施設の修了+国家試験 |
| 国家試験の合格率 | 約30〜60% | 約60~70% |
※合格率は、2020年~2025年のデータを参照しています。
参考:社会福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移(厚生労働省HPより)
精神保健福祉士国家試験の受験者・合格者の推移(厚生労働省HPより)
違い①:支援する「対象者」の範囲
社会福祉士と精神保健福祉士が支援する対象者は以下のとおりです。
| 社会福祉士 | 高齢者、障がい者、児童、生活困窮者など、あらゆる生活課題を抱える人々 |
| 精神保健福祉士 | 精神疾患・発達障がいを抱える人やそのご家族 |
それぞれ支援対象が重なる場合もありますが、社会福祉士は地域で生活するあらゆる生活課題を抱える人、精神保健福祉士は、精神疾患や依存症、発達障がいを抱える人に特化して相談援助を行います。
違い②:主な「仕事内容」と「活躍する職場」
社会福祉士と精神保健福祉士の仕事内容や活躍の場は以下のようになっています。
| 社会福祉士 | 福祉事務所、社会福祉協議会、高齢者施設、障がい者施設、児童施設、医療機関、学校などで課題を抱える人たちの相談にのり、必要な福祉サービスの利用支援や権利擁護支援などを行う |
| 精神保健福祉士 | 精神科病院やクリニック、障がい者施設、保健センターなどの行政機関、企業などで、入退院や社会復帰支援、地域生活を送るうえでの環境の調整や、産業保健領域でメンタルヘルスに関する業務を行う |
どちらもソーシャルワーカーとして、さまざまな専門職や機関と連携しながら課題を抱えた人を対象に相談援助を行いますが、精神保健福祉士は精神疾患や精神障害のある人に特化した支援を行うのに対し、社会福祉士は福祉サービスを必要とするすべての人を対象としています。
そのため、活躍の場も多岐にわたっています。
違い③「資格取得ルート」と「試験の難易度・合格率」
受験資格を得るためには、社会福祉士は12通り、精神保健福祉士は11通りのルートがあります。
主なルートは以下のとおりです。
- 保健福祉系4年生大学で指定科目を履修し卒業する
- 保健福祉系短大や専門学校で指定科目を履修したのち、相談援助の実務経験を2年積む
- 一般大学卒業後、社会福祉士または精神保健福祉士の一般養成施設で、指定科目を履修する。
- 短大卒業後、指定された施設において相談援助の実務経験を積んでから養成施設に進み、指定科目を履修する。
受験資格の要件は細やかに設定されていますので、詳細は社会福祉振興・試験センターのHPなどでご確認ください。
出典:社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士の合格率は、例年30%前後で推移していましたが、令和5年度、令和6年度は50%を超え、合格率は上がってきています。
一方精神保健福祉士国家試験も、例年60%代だった合格率が令和6年度では70.7%と上昇しています。
ダブルライセンスの3大メリット
社会福祉士と精神保健福祉士を両方所持するメリットについては、以下の3点が挙げられます。
支援の専門性が深まり、対応できる業務の幅が広がる
社会福祉士や精神保健福祉士が支援の対象とする方々は、複数の課題を抱えていたり、世帯内に課題を抱える多世代の人が同居していたりすることも少なくありません。
たとえば、高齢者の介護をする同居の子どもに精神障がいがある場合や、精神疾患を抱えた人が子育ての支援を必要としたり、生活に困窮したりといったことも頻繁にあります。
ダブルライセンスを取得することで、幅広く深い知識が身に付き、対応できる業務の幅が広がります。
そのため、より質の高い支援ができるようになります。
就職・転職で有利になり、キャリアの選択肢が広がる
ダブルライセンスを取得することで、ソーシャルワーカーとしての汎用性が高くなります。
複数の部署を有する多機能型の事業所では、人事異動の際にも重宝するため、採用の際に有利に働くこともあるでしょう。
また、高齢者の介護や福祉に関する相談機関である地域包括支援センターでは社会福祉士が必置になっており、精神科病院や精神科訪問看護などでは精神保健福祉士の配置が加算の対象になっています。
両方の資格を取得していることで、あらゆる領域へ就職する選択肢が増えます。
資格手当による年収・給料アップが期待できる
多くの事業所では、上記の国家資格を取得していることで、「資格手当」が支給されることがあります。
また、2つの資格を取得していることでソーシャルワーカーとしての対応力が向上し、管理職などへの道がひらけ、結果的に年収アップにつながるケースもあるようです。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表している令和2年度の就労状況調査の報告書によると、平均年収は社会福祉士が403万円、精神保健福祉士が404万円と、大きな差はありません。
資格手当がある職場は35%前後で、平均額は10,000~12,000円となっています。
出典:社会福祉士就労状況調査実施結果報告書(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
精神保健福祉士就労状況調査実施結果報告書(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
ダブルライセンスを目指す!効率的な資格取得ルートと学習法
ダブルライセンスを取得するためにはどのように学習計画を立てていけばよいのでしょうか。
具体的には以下のポイントが挙げられます。
国家試験の「共通科目免除」制度を最大限活用する
社会福祉士と精神保健福祉士の国家試験には、どちらの試験にも共通した12科目の共通科目があります。
先にいずれかの資格を取得した場合、もう一方の試験を受ける際に、共通科目の受験は免除されます。
この制度を活用することで、学習時間の短縮や精神的負担の軽減が可能になります。
社会福祉士と精神保健福祉士の資格取得のおすすめの順番は?
一般的には、先に社会福祉士を取得してから精神保健福祉士を目指すルートが王道とされています。
理由として、精神保健福祉士の養成施設には、一般養成課程(1年~1年9か月)と短期養成課程(半年~1年)がありますが、社会福祉士を取得している場合、短期養成課程で学ぶことができるからです。(精神保健福祉士から社会福祉士を目指す場合は、精神保健福祉士を取得したルートによって一般養成課程か短期養成課程かが変わるため、養成校等へご確認ください。)
そのため、ダブルライセンスを検討しているのであれば、社会福祉士から先に取得する方が、短期間の資格取得が可能になります。
ただし、条件によって異なる為、詳しくは公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのHPをご確認ください。
また、社会福祉士の受験科目は幅広い福祉に関する知識や歴史、さまざまな分野の制度などを学ぶため、先に福祉の全体像や流れを掴んだうえで、精神保健福祉領域の専門分野について学ぶことで学習するうえでも理解しやすい流れになります。
通信制大学や養成施設(短期・一般)の選び方のポイント
福祉系の大学を卒業していない人が、社会福祉士や精神保健福祉士を取得する場合、受験資格を得るために養成施設や通信制大学に通うことが必要となります。
働きながら資格を取得する場合は、通信制の養成校や大学を選ぶことで両立がしやすくなります。
スクーリングなどで対面での講義の受講が必要な場合もありますが、最近ではオンライン授業なども充実しています。
レポート提出が必要となることが多いので、計画的に学習を進める必要があるでしょう。
中には夜間の通学課程を設けている養成施設もあります。通信課程での学習は不安だけれど、仕事とも両立したいという方にはおすすめです。
いずれの場合も、実務経験で実習が免除にならない場合は、相談援助実習が必須となります。
この場合、まとまった期間(210~240時間)仕事を休まなければならない可能性もあることを視野に入れましょう。
中には、何週かにかけて、数日ずつ分散して実習に応じてくれる施設や、土日に実習対応してくれる施設を実習先施設として紹介していただける場合もあります。
その他、学費や実習、国家試験のサポート体制などを基準に、資料請求や説明会へ参加するなどし、自分に合った養成校や大学を見つけましょう。
よくある質問FAQ
まとめ
社会福祉士は、生活に課題を抱えるあらゆる人を対象に、精神保健福祉士は、より精神保健分野に特化した福祉の専門職として、どちらも社会から必要とされている存在です。
それぞれの違いや役割を理解し、将来のビジョンに合わせた選択をすることが大切です。
両資格を取得することで支援の幅が広がり、就職・転職の選択肢が増えるほか、年収増加やキャリアアップの可能性もあります。
ぜひ、この記事を参考に、あなたの理想のキャリアに近づくための第一歩を踏み出してください。
「ケア人材バンク」では社会福祉士や精神保健福祉士の資格を活かした就職や転職に関する情報も紹介しています。
専門のエージェントが親身になって相談にのっておりますので、悩んだ際はぜひご活用ください。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。