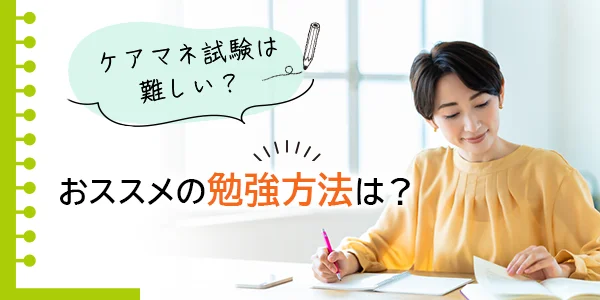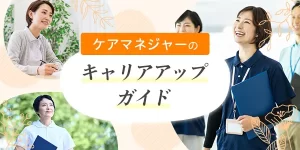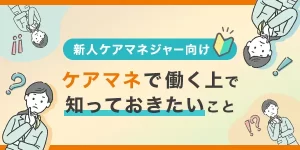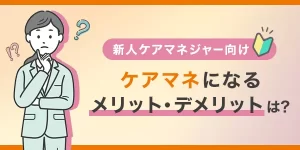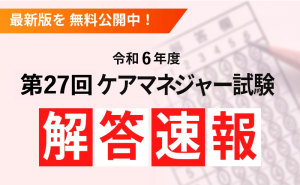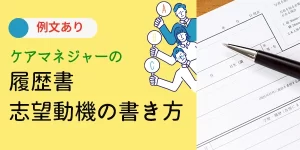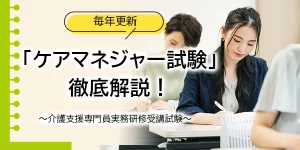介護の仕事をしている方であれば、キャリアアップとしてケアマネジャー試験の合格を目指す方が多いのではないでしょうか。
しかし、ケアマネジャー試験は他の介護系資格と比較すると難易度が高いと言われています。仕事をしながら受験する方も多く、合格できるのか不安を感じている方もいるでしょう。
この記事では、ケアマネジャー試験の概要や難易度、勉強法などについて詳しく解説します。
是非、今後のケアマネ試験の合格率・合格ライン予想の参考にしてください。
目次
ケアマネジャー試験の合格率・合格者数
2024年度のケアマネジャー試験の受験者数や合格率はこちらとなります。
第27回(2024年度)ケアマネ試験結果について
まずは、第27回(2024年度)のケアマネジャー試験の結果は以下の通りです。
受験者数:53,699人
合格者数:17,228人
2024年度のケアマネ試験の合格率は32.1%でした。
出典:第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について(厚生労働省)
ケアマネ試験に合格するには何点取ればいい?
ケアマネジャー試験の出題分野は、以下の2分野です。
- 「介護支援分野」25問
- 「保健医療福祉サービス分野」35問
過去5年のケアマネジャー試験の合格基準ラインは、以下の通りです。
| 介護支援分野 (全25問) | 保健医療福祉サービス分野 (全35問) | 合格基準ライン | |
|---|---|---|---|
| 第27回 (2024年度) | 18点 正答率:72.0% | 25点 正答率:71.4% | 71.7% |
| 第26回 (2023年度) | 17点 正答率:68.0% | 24点 正答率:68.6% | 68.3% |
| 第25回 (2022年度) | 18点 正答率:72.0% | 26点 正答率:74.3% | 73.3% |
| 第24回 (2021年度) | 14点 正答率:56.0% | 25点 正答率:71.4% | 65.0% |
| 第23回 (2020年度) | 13点 正答率:52.0% | 22点 正答率:62.9% | 58.3% |
ケアマネジャー試験は、介護支援分野・保健医療福祉サービス分野で合計60問が出題され、正答率70%以上が合格ラインとされています。
令和4年度の正答率は高く、2分野とも70%を超えていましたが、令和5年度は70%を下回る合格基準ラインとなりました。
ケアマネ試験の合格点はどうやって決まっている?
ケアマネジャー試験の合格ラインは正答率70%が基準ですが、その年度の試験難易度で点数が補正されます。
前述したように、過去5年間では、2022年度以外は、合格者は正答率が70%を下回っていましたが難易度により合格ラインが調整されました。難易度が高い年度では正答率が70%以下でも合格しますが、70%以上を目指して得点できるようにしておくと安心です。
ケアマネ試験の合格率はどのくらい?
ケアマネジャー試験の合格率はこれまで20%前後でした。これは、他の福祉系資格に比べると難関です。
2018年度から、ケアマネジャーの質を向上させるために、受験資格が厳しくなったことも影響しています。受験資格が厳格化されたことにより、受験対象者が少なくなり受験者も半分以上減少しています。
ただし、2024年度はこれまでのケアマネ試験よりも合格率が大幅に上昇したため、ケアマネ試験の難易度の傾向も、今後変わっていく可能性があります。
ケアマネ試験で合格率の高い都道府県(2024年度)
次に、2024年度のケアマネ試験の都道府県別の合格率をみてみましょう。
| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,843 | 852 | 29.97% |
| 青森県 | 831 | 185 | 22.26% |
| 岩手県 | 627 | 176 | 28.07% |
| 宮城県 | 1,096 | 298 | 27.19% |
| 秋田県 | 512 | 138 | 26.95% |
| 山形県 | 584 | 141 | 24.14% |
| 福島県 | 921 | 278 | 30.18% |
| 茨城県 | 1,114 | 322 | 28.90% |
| 栃木県 | 636 | 232 | 36.48% |
| 群馬県 | 880 | 263 | 29.89% |
| 埼玉県 | 2,549 | 933 | 36.60% |
| 千葉県 | 2,193 | 735 | 33.52% |
| 東京都 | 4,493 | 1629 | 36.26% |
| 神奈川県 | 3,263 | 1176 | 36.04% |
| 新潟県 | 884 | 290 | 32.81% |
| 富山県 | 518 | 173 | 33.40% |
| 石川県 | 445 | 159 | 35.73% |
| 福井県 | 357 | 119 | 33.33% |
| 山梨県 | 314 | 106 | 33.76% |
| 長野県 | 982 | 299 | 30.45% |
| 岐阜県 | 806 | 281 | 34.86% |
| 静岡県 | 1,374 | 452 | 32.90% |
| 愛知県 | 2,353 | 926 | 39.35% |
| 三重県 | 836 | 250 | 29.90% |
| 滋賀県 | 598 | 215 | 35.95% |
| 京都府 | 1,309 | 481 | 36.75% |
| 大阪府 | 3,826 | 1195 | 31.23% |
| 兵庫県 | 2,522 | 744 | 29.50% |
| 奈良県 | 621 | 196 | 31.56% |
| 和歌山県 | 500 | 139 | 27.80% |
| 鳥取県 | 334 | 82 | 24.55% |
| 島根県 | 487 | 107 | 21.97% |
| 岡山県 | 1,073 | 324 | 30.20% |
| 広島県 | 1,352 | 442 | 32.69% |
| 山口県 | 682 | 207 | 30.35% |
| 徳島県 | 449 | 115 | 25.61% |
| 香川県 | 385 | 137 | 35.58% |
| 愛媛県 | 701 | 211 | 30.10% |
| 高知県 | 449 | 109 | 24.28% |
| 福岡県 | 2,002 | 676 | 33.77% |
| 佐賀県 | 451 | 117 | 25.94% |
| 長崎県 | 705 | 179 | 25.39% |
| 熊本県 | 930 | 264 | 28.39% |
| 大分県 | 586 | 165 | 28.16% |
| 宮崎県 | 652 | 165 | 25.31% |
| 鹿児島県 | 953 | 253 | 26.55% |
| 沖縄県 | 731 | 219 | 29.96% |
| 合計 | 53,709 | 17,155 | 32.1% |
都道府県別では、トップが愛知県で39.35%となっていて、前回の2023年度も25.41%と全都道府県でトップの合格率でした。
その他、各都道府県の合格率の上位5地域は以下の通りです。
1.愛知県(39.35%)
2.京都府(36.75%)
3.埼玉県(36.6%)
4.栃木県(36.48%)
5.東京都(36.26%)
過去のケアマネジャー試験の受験者と合格率
過去10年間のケアマネ試験の受験者と合格率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 介護支援分野 合格基準点 | 保健医療福祉サービス分野 合格基準点 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第27回 (2024年度) | 53,699人 | 17,228人 | 18点 | 25点 | 32.1% |
| 第26回 (2023年度) | 56,494人 | 11,844人 | 17点 | 24点 | 21.0% |
| 第25回 (2022年度) | 54,406人 | 10,328人 | 18点 | 26点 | 19.0% |
| 第24回 (2021年度) | 54,290人 | 12,662人 | 14点 | 25点 | 23.3% |
| 第23回 (2020年度) | 46,415人 | 8,200人 | 13点 | 22点 | 17.7% |
| 第22回 (2019年度) | 41,049人 | 8,018人 | 16点 | 25点 | 19.5% |
| 第21回 (2018年度) | 49,332人 | 4,990人 | 13点 | 22点 | 10.1% |
| 第20回 (2017年度) | 131,560人 | 28,233人 | 15点 | 23点 | 21.5% |
| 第19回 (2016年度) | 124,585人 | 16,281人 | 13点 | 22点 | 13.1% |
| 第18回 (2015年度) | 134,539人 | 20,924人 | 13点 | 25点 | 15.6% |
出典:介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況等(厚生労働省)
2025年度のケアマネジャー試験の合格率は?
過去5年間のケアマネ合格率のデータから、2025年度の傾向を予想してみましょう。
改めて、改正後からのケアマネ試験の合格率の推移を見ると、過去5年間の平均合格率は22.69%となっております。
過去3年の平均は23.89%、過去2年の平均は26.31%と、2024年度の高い合格率によって、平均の合格率は上昇傾向です。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2020年度 | 17.67% |
| 2021年度 | 23.32% |
| 2022年度 | 18.98% |
| 2023年度 | 20.97% |
| 2024年度 | 32.1% |
| 合格率 | |
|---|---|
| 過去5年間平均 (2024~2020年度) | 22.69% |
| 過去3年間平均 (2024~2022年度) | 23.89% |
| 過去2年平均 (2024、2023年度) | 26.31% |
昨今のケアマネジャーの人手不足等を受けて、2024年度のケアマネ試験の難易度は下げられた可能性もありますが、2025年度も高い合格率が続くのでしょうか。
ケアマネジャー試験について
まずは、試験の出題形式や合格点、合格率についての概要を確認してみましょう。
ケアマネ試験の出題形式
ケアマネジャー試験の出題形式は「五肢複択式」のマークシートです。五肢複択式とは、5つの選択肢の中から正しい回答を複数選択する方式です。
五肢複択式の場合、確実な理解をしていなければ正答することが難しくなるため、正確な知識が問われる出題方式だと言えます。
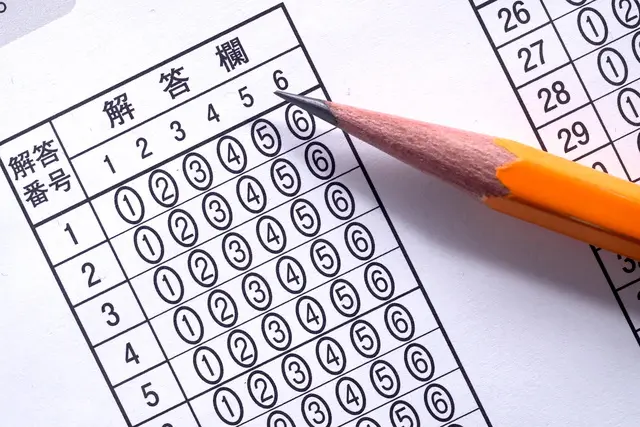
過去のケアマネ試験の出題傾向は?
ここ最近でケアマネ試験の出題傾向のポイントは以下の通りです。
- 基本的な内容の出題が多い
- 介護保険法第5条についても出題されている
- 「重層的支援体制整備事業」についても出題されている
- 事例問題は3問程度
ここ最近でのケアマネ試験は、例年通りの基本的な内容の出題が多かった印象です。
介護保険制度については例年、介護保険法の第1条・2条・4条について出題されることが多かったのですが、第25回の試験では介護保険法第5条について出題されました。
また、2021年4月に施行された社会福祉法の「重層的支援体制整備事業」についても出題されています。
事例問題は、毎年2問〜3問出題されています。
保健医療福祉サービス分野は、比較的回答しやすかったという意見が多かったようです。
参考:東京都福祉保健局 介護支援専門員実務研修受講試験問題(令和4年度 第25回)
ケアマネジャー試験の難易度
ケアマネジャー試験はなぜほかの介護系資格より難易度が高いと言われるのでしょうか。理由をみていきましょう。

ケアマネ試験の合格率はなぜ低い?
ケアマネ試験の合格率が低い理由には、以下のことが考えられます。
- ケアマネの質を向上するために合格基準が厳格化された
- 試験勉強の時間の確保が難しい
- 解答方式が五肢複択方式のため正確な知識が必要
- 知識のアップデートが必要
それぞれについて詳しく確認していきます。
ケアマネの質を向上するために合格基準が厳格化された
日本の超高齢化が進む中、ケアマネジャーの仕事は非常に重要です。専門的な知識や経験を積んだ質の高いケアマネジャーが求められており、2018年には受験資格が厳格化されています。
2018年度からのケアマネジャーの試験を受験できるのは、国家資格所有者もしくは、相談援助業務についている人が要件となりました。要件を満たした上、5年以上実務経験が必要なため、2018年度以降の受験者数は急激に落ち込んでいます。
ケアマネジャー試験に合格する人が増えれば、介護現場で働く介護福祉士が減少することも懸念されています。ケアマネジャーも必要ですが、現場で働く介護スタッフの人手不足はさらに深刻です。試験の難易度を上げてバランスを取っているのでないかとも言われています。
試験勉強の時間の確保が難しい
ケアマネ試験受験するには実務経験が必要なため、就業しながら試験に挑む方が大半です。人手不足の介護現場では、慢性的な残業が続いている職場で働いている方も多いのではないでしょうか。そのような方は、仕事をしながら試験勉強の時間を十分に確保するのが難しくなります。勉強時間が確保できたとしても、介護現場での体力的な疲労や相談業務などの精神的な疲労で、勉強する体力・気力を維持するのが難しいかもしれません。
ケアマネ試験の受験者は5年以上の実務経験を備えた方であり、職場でも重要なポジションを任されている方も少なくありません。普段の介護業務に加え、さらに任務が課せられて激務が続いている方もいるでしょう。さらに、家庭を持っている方であれば、家事や育児などとの両立も困難になります。
十分に時間を取って勉強できる環境にある方が少ないのも、ケアマネ試験の合格率が低くなってしまう理由の一つです。
解答方式が五肢複択方式のため正確な知識が必要
前述した通り、ケアマネ試験の解答方式は五肢複択方式です。5つの選択肢の中から2つもしくは3つの正しい回答を選択するため、正確な知識が問われます。
介護福祉士試験で採用されているような、正しいものを1つ選択する五肢択一式であれば消去法で正答率が上がり、全く分からない問題であっても1/5の確率で正解することも可能です。
五肢複択方式は正しい選択ができたとしても、他の選択肢が1つでも間違っていればその問題は正答にはなりません。幅広く正確な知識が必要になる、難易度が高い出題方式だと言えます。
知識のアップデートが必要
介護保険制度は、新しい制度が導入されるたび知識をアップデートさせなければなりません。法改正が行われた年は、新しい知識も必要になるため、試験の難易度が上がります。
法改正に関連する問題の出題数は年度によって変わりますが、過去問だけではなく最新情報に対する知識も求められるため、試験対策の難易度を上げています。
どんな出題が難しい?
ケアマネの試験では、介護や医療の専門的な用語や内容を把握しておくことが大切です。
「介護支援分野」「保健医療福祉サービス分野」の両分野どちらも基準点に達することが必要ですが、特に難しいと言われるのが介護支援分野です。
毎年よく出題される内容は以下の通りです。
- 要介護認定や介護認定審査会について
- 介護保険の保険者について
- 介護保険制度について
- ケアマネジメントについて
- サービス事業所について
- 介護予防支援について
介護支援分野は、複雑な制度や事業に関する問題が出題されるため反復学習しなければ、なかなか覚えられません。似たような名前の制度や法律も多いので内容をしっかり把握しておくことが必要になります。
よく出題される問題に、それぞれの制度の管轄が国なのか都道府県なのか市町村なのかという問題があります。制度を理解する際は制度の主体など、全体像も把握しておくようにしましょう。
他の医療・介護福祉の資格と比べて難易度は?
ケアマネジャー資格の難易度を他の医療系資格・福祉系資格と比較してみました。
| 資格名 | 2023年度合格率 |
|---|---|
| 介護支援専門員 | 21.0% |
| 介護福祉士 | 82.8% |
| 社会福祉士 | 58.1% |
| 精神保健福祉士 | 70.4% |
| 看護師 | 87.8% |
| 理学療法士 | 89.2% |
| 作業療法士 | 84.1% |
参考:第36回介護福祉士国家試験合格発表(厚生労働省)
第36回社会福祉士国家試験合格発表(厚生労働省)
第26回精神保健福祉士国家試験合格結果(厚生労働省)
第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験及び第113回看護師国家試験の合格発表(厚生労働省)
第59回理学療法士国家試験及び第59回作業療法士国家試験の合格発表(厚生労働省)
ケアマネ試験の合格率は20%前後であり、医療・介護系の資格に比べると低いことがわかります。ただし、専門学校等に数年通った上で受験するような資格も含まれているため、独学での受験者が多いケアマネジャー試験と難易度を比較するのは困難です。
ケアマネと社会福祉士はどちらが難しい?
社会福祉士の資格は、国家資格の為、民間資格のケアマネジャーとは、資格の種類が異なりますが、合格率で比較すると、ケアマネジャーの資格取得の方が合格率が低く、難易度が高い結果となります。
- 社会福祉士の平均合格率:約30%~45%
- ケアマネジャーの平均合格率:20%前後
職種が異なるため、一概には言えませんが、この結果を見ると、社会福祉士よりも、ケアマネジャー試験の方が難しいと言えます。
ただし、2024年度の社会福祉士の国家試験は、試験にでる科目のカリキュラムが新しい科目に変更される為、今後の社会福祉士の難易度が変化する可能性があります。
ケアマネと看護師はどちらが難しい?
看護師の資格は、国家資格の為、民間資格のケアマネジャーとは、資格の種類が異なりますが、合格率で比較すると、ケアマネジャーの資格取得の方が合格率が低く、難易度が高い結果となります。
- 看護師の平均合格率:約80%~90%
- ケアマネジャーの平均合格率:20%前後
職種が異なるため、一概には言えませんが、この結果を見ると、看護師よりも、ケアマネジャー試験の方が難しいと言えます。
試験合格に向けての勉強時間
独学でも合格できる?
ケアマネジャー試験を受験する人の多くは、仕事をしながら受験する方も多く、仕事と両立しながら、独学で勉強して受験される方も多くいて、難易度の高さの要因の一つでもあると言われています。
そのため、独学で勉強する場合は、効率よく学習を進める必要があります。
おすすめの勉強方法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
どのくらい勉強すれば合格できる?
一般的に、ケアマネ試験を受験する方の勉強時間は100~200時間と言われています。
ただし、100時間と200時間とでは、倍の差があるため、あくまで参考程度ととらえてください。
大事なのは、仕事と試験勉強を両立できる無理のない範囲で勉強時間を確保する場合、
「1日あたりの勉強時間をあまり取れないのであれば、半年前から試験勉強を始める。」というように、試験勉強の開始時期も含めて、計画的に試験対策することで、計画的に試験勉強を進めることができるでしょう。
試験合格に向けてのおすすめ勉強法
ケアマネ試験は合格率が低いと言われますが、コツをつかんで勉強すれば合格に近づくことができます。
試験の情報や対策などをX(エックス)※旧ツイッターなどのSNSで収集している方も多いようです。
時間の確保が難しい方も多いため効率よく学習できるようにしましょう。
勉強法のコツは以下の通りです。
- 試験までの学習計画を立てる
- 適切な参考書を選ぶ
- 過去問で出題傾向をつかむ
- 法改正や時事問題もチェック
それぞれについて詳しく解説します。
試験までの学習計画を立てる
ケアマネ試験に合格するには、仕事と勉強の両立が鍵です。仕事が忙しいことが理由で勉強時間が確保できないままでいると、あっという間に試験日になってしまいます。勉強はできるだけ早めに開始し、余裕を持たせた大まかな予定を立てましょう。
ケアマネ試験受験者は就業している方が大半です。隙間時間を活用し、数分でも良いので参考書を開く習慣をつけることが大切です。
参考書で全体を把握し、試験日が近づいて来たら時間配分を意識しながら過去問や模擬試験にチャレンジすると、試験当日のシミュレーションになるでしょう。

適切な参考書を選ぶ
ケアマネ試験に合格するための勉強には、適切な参考書選びも重要です。
ケアマネ試験の参考書は、図解などを利用し解説が充実しているものを選ぶのがおすすめです。図解・表・イラストなどでわかりやすく解説しているタイプは、全体像がイメージできるので頭に入りやすく勉強が進めやすくなります。
1つのテキストが一通り終わったら、新しいテキストを購入したくなる方がいるかもしれません。しかし、複数のテキストで勉強するより1つのテキストを繰り返して勉強する方がおすすめです。自分にあったテキストを徹底的に読み込み理解しましょう。1つのテキストで繰り返し学習することで、自分の苦手な項目もはっきりして理解が深められます。
試験を受ける方の中には、以前受験した先輩の参考書を譲ってもらう方もいるかもしれません。その場合は、法改正に対応しているかを確認することが大切です。制度が変わっているのにもかかわらず、古い情報のまま学習してしまわないように注意しましょう。
過去問で出題傾向をつかむ
ケアマネ試験の勉強では、過去問を解いて出題傾向をつかんでおくことは非常に重要です。過去問を解くことで出題される問題の雰囲気がつかめます。どのような問題で引っかかりやすいかもイメージできます。
ただし、法令や規則が変更される前の情報が出題されている可能性もあるため、あまりにも古い過去問までする必要はありません。
介護保険制度の改正が5年に1回、報酬の改定は3年に1回あるため、過去3年〜5年くらいにとどめておくと良いでしょう。
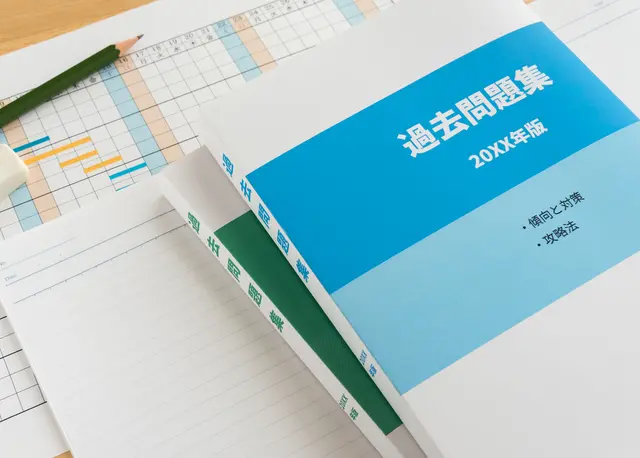
法改正や時事問題もチェック
参考書や過去問を解くことで試験の出題傾向がつかめますが、ケアマネ試験では最近の時事問題から出題されるケースがあります。また、法改正の後には新しい制度改正に関する問題も数問出題されています。
これらの新しい情報は参考書では対応できないため、ニュースや新聞などの時事問題や新しい制度に関する情報は必ずチェックしておきましょう。
まとめ
今回の記事では、ケアマネ試験について解説しました。
ケアマネジャー資格は超高齢社会において、ますます需要が高まる資格に位置付けられることが予想されます。受験資格が厳格化され合格率も低い資格ですが、それだけ価値のある資格です。
仕事と勉強の両立は簡単なものではありませんが、資格取得のプロセスも含め自身の力になるはずです。
介護職の方のキャリアアップとしてぜひ資格取得を検討してみてください。
「ケア人材バンク」では、ケアマネ専門の転職エージェントが、完全無料で転職を徹底サポートいたします。ケアマネジャー試験を受験する方のご登録も大歓迎です!
この機会に是非ご登録ください。