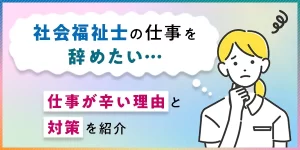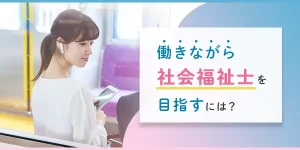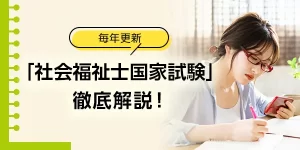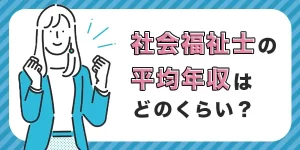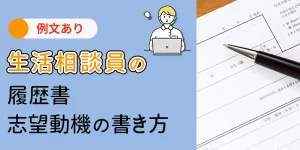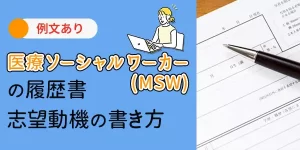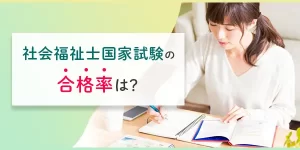「老健で社会福祉士として働いてみたいけれど、どんな仕事をするの?」
「特養との違いは何?」
社会福祉士の資格を活かした働き方をする上で、こんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
介護老人保健施設(老健)は、病院と在宅の”中間施設”として利用者様の在宅復帰を支える重要な役割を担っています。
社会福祉士として働くことで、医療・介護・福祉の架け橋となり、高齢者とそのご家族を支えるやりがいある現場です
目次
- 老健の社会福祉士(相談員)は、入退所支援から関係各所との連携まで、利用者様の生活と在宅復帰を支える「調整役のプロ」です。
- 「特養」と「老健」の違いは、施設に求められる役割や目的です。
- 就職・転職する際には、老健での仕事の鍵は「連携力・調整力」が活かせるかどうかの見極めが重要。
介護老人保健施設(老健)とは?特養との違いは「目的」
老健での社会福祉士の仕事を理解するには、まず「老健とはどんな施設なのか」を知ることが重要です。特養との違いを整理しながら、役割の背景を理解しましょう。
老健の目的は「在宅復帰」を支援する中間施設
老健(介護老人保健施設)は、病院と自宅の中間にあるリハビリ施設です。
病気や怪我で入院していた高齢者が、自宅へ戻るためのリハビリや生活訓練を行う場であり、医師・看護師・介護職・リハビリ職・社会福祉士などがチームとなって支援します。
老健の入所期間は3〜6ヶ月が目安です。短期間で成果を出す必要があるため、社会福祉士には迅速な課題整理や情報共有、他職種調整が求められます。
そして、在宅復帰を目指す利用者様の”生活の方向性”を描き、家族・地域とつなぐ存在となるのです。

特養(特別養護老人ホーム)の目的は「長期的な生活の場」としての生活支援
一方、特養(特別養護老人ホーム)は、「終(つい)のすみか」としての役割を持つ施設です。要介護3以上の方が中心で、在宅復帰よりも”安心して長く暮らせる生活支援”に重点が置かれます。
ここでは、社会福祉士は入居者様やご家族の生活全般を長期的に支え、人生に寄り添う支援を行います。つまり、老健と特養では「ゴール」が全く異なるため、それに伴って求められる社会福祉士の役割や姿勢も変わります。
目的が違うからこそ、社会福祉に求められる役割も変わる
社会福祉士の役割は、老健では「在宅復帰に向けた支援と調整」、特養では「長期的な安心の伴走支援」となっています。
老健の社会福祉士はスピード感と柔軟性が求められ、特養の社会福祉士は継続的な信頼関係の構築が重要です。
どちらも人の暮らしを支える仕事ですが、老健ではより深い「調整力」が試される場面が多いといえます。

老健で働く社会福祉士(相談員)の4つの主な仕事内容
老健の社会福祉士は「入退所支援の窓口」としてだけでなく、利用者様・ご家族・他職種・地域をつなぐ「橋渡し役」です。
主な仕事内容として、以下の4つが挙げられます。
入所・退所支援(相談業務の最重要部分)
相談員業務の中心は、入退所に関する相談と調整です。
病院やケアマネジャー、ご家族からの問い合わせを受け、利用者様の情報を整理・確認します。
医療面や介護度、家庭状況を考慮して受け入れ可能かを判断し、医師や看護師と連携して入所を調整します。また、入所時には契約説明や必要書類の準備、リハビリ方針の共有なども行います。
なお、退所時には在宅復帰や他施設への移行がスムーズに進むよう、ケアマネや地域包括支援センター、訪問介護などと連携して、退所後も安心できる環境を整えます。
他職種との連携・調整業務
老健の社会福祉士は、医師・看護師・介護士・リハビリ職・管理栄養士など他職種の「潤滑油」的な役割を担います。
カンファレンスでは、利用者様の在宅復帰計画を共有し、ご家族との方向性のすり合わせや医療的リスクの確認を行います。
この調整力が、老健で活躍できる社会福祉士のやりがいであり強みとなります。
専門職同士の立場を尊重しながら、チーム全体が同じ方向に進むようにまとめていく力が求められるのです。
ご家族との連絡・調整、相談対応
利用者様ご本人だけでなく、ご家族への支援も欠かせません。
特に退所支援では、「自宅で介護できるか不安」「サービスをどう使えば良いかわからない」といったご家族の不安を受け止め、具体的な支援策を提示します。
社会福祉士は、心理的支えとなりつつ、制度面・地域資源を活用した支援策を示す専門職でもあります。
「話を聞いてくれて安心した」と言われることが多く、やりがいを感じる場面の一つです。

④地域の関連機関との連携(ケアマネジャー、病院など)
老健の相談員は、地域の医療・介護ネットワークのハブ的存在です。
病院の退院調整看護師や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などと密に連携します。
在宅復帰後も継続的に支援が続くよう、訪問介護・デイサービス・ショートステイなどと情報共有を行い、「途切れない支援」を目指します。
地域全体を見渡しながら必要な調整を行うため、「司令塔」のような役割を担っていると言えるでしょう。
【タイムスケジュール】老健の社会福祉士、1日の仕事の流れは?
では、実際に老健で働く社会福祉士の1日はどのように進むのでしょうか。
朝から夕方までのスケジュールを例として、働き方を紹介します。
| 時間 | 業務内容 |
|---|---|
| 8:30 | 出勤・申し送り・メール確認 |
| 9:00 | 新規入所希望者の確認・病院との連絡 |
| 10:00 | 入所時説明・契約対応 |
| 11:00 | カンファレンス(多職種会議) |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 家族面談・退所支援の打ち合わせ |
| 15:00 | ケアマネジャー・地域包括支援センターとの調整 |
| 16:30 | 記録作成・翌日の調整業務 |
| 17:30 | 退勤 |
日中は来客対応や会議が多く、「気付くと夕方だ」ということが珍しくありません。
多様な立場の人と関わるため、コミュニケーション力・柔軟性・調整力が求められる仕事といえます。
気になる給料は?老健の社会福祉士の平均年収
転職を検討する際、どうしても気になるのが給与面です。
ここでは、老健で働く社会福祉士の平均年収と、収入アップのポイントを見ていきましょう。
平均年収の目安
老健の社会福祉士(相談員)の平均年収は、令和2年度の社会福祉士就労状況調査実施結果報告書によると、正規職員の相談員の年収が391万円、介護老人保健施設の年収は392万円のため、390万円前後の年収であると想定できます。
その後、経験や役職、資格が考慮されて、昇給していく形になります。
介護職よりやや高く、看護職よりやや低い水準となっており、賞与や手当が充実している法人も多いことから、夜勤がない分ワークライフバランスが取りやすい傾向があります。
出典:令和2年度_社会福祉士就労状況調査実施結果報告書(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
給与アップを目指すためのポイント(役職、資格手当など)
老健の社会福祉士として給与を上げていくためのポイントとしては、「主任相談員」や「課長」といった役職によるアップやケアマネ(介護支援専門員)の資格取得が挙げられます。
また、医療法人が運営する老健では、病院との人事連携があるケースもあり、キャリアアップのチャンスが広がる傾向にあります。
老健の社会福祉士に関するよくある質問
老健で働く社会福祉士を目指す人からよく寄せられる質問にお答えします。
まとめ
老健で働く社会福祉士は、利用者様の「在宅復帰」という目標を支えるチームの中心となる仕事です。入退所の調整から家族支援、地域連携まで幅広く関わるため、人とのつながりを感じながら働くことができます。
一方で、施設ごとに業務範囲やチーム体制、給与水準が大きく異なります。そのため、自分に合った環境でキャリアを築くには、業界に詳しい転職エージェントのサポートを活用するのが近道です。
老健の社会福祉士に転職するなら「ケア人材バンク」
老健の社会福祉士求人は、非公開のものも多くあります。また、施設ごとの雰囲気や運営方針は外から見えにくいものです。
そんな時は、介護・福祉業界に特化した転職支援サービス「ケア人材バンク」にお気軽にご相談ください。
ケア人材バンクでは、専任のキャリアパートナーがあなたの希望に合った老健の求人を無料で紹介します。また、面接対策や条件交渉も徹底的にサポートしますのでご安心ください。
「在宅復帰支援に関わりたい」「社会福祉士として次のステージに進みたい」
そんな方の挑戦を、しっかりサポートさせていただきます。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。