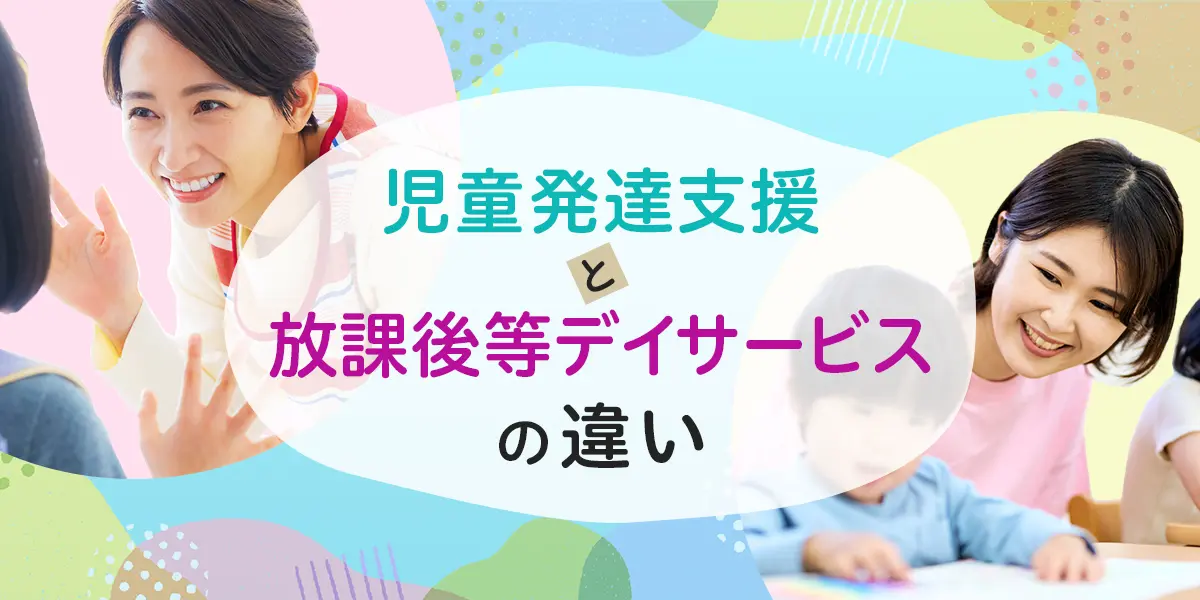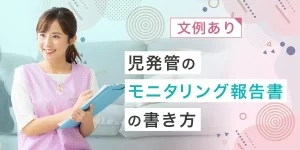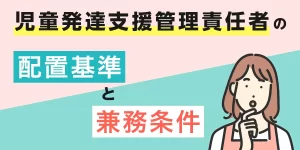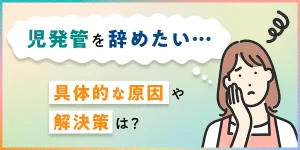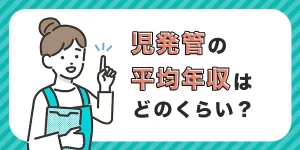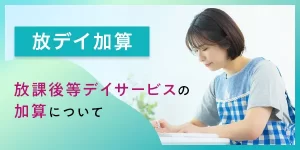児童発達支援と放課後等デイサービス(放デイ)では、共通する部分もありますが、対象年齢や利用目的など、異なる点もいくつか存在します。
目次
児童発達支援と放デイの最大の違いは「対象年齢」
児童発達支援と放デイは、どちらも発達に特性のあるお子さんを支援する福祉サービスですが、最も大きな違いは対象年齢です。
まずは、どの年齢層のお子様が利用できるかを確認していきましょう。
児童発達支援は未就学児(おおむね0〜6歳)対象
児童発達支援の対象は、おおむね0歳から6歳までの未就学児です。
未就学児とは小学校入学前の子どもを指し、保育園、幼稚園、こども園などに通う年齢層が中心です。
就学前の発達支援や生活習慣の形成を目的としており、利用期間は基本的に小学校入学前までとなります。
ただし、事業所や自治体によって「◯歳から」「◯歳まで」と受け入れ年齢を限定しているケースもあるため、働く際には自施設の受け入れ年齢範囲を確認しておくことが重要です。
放課後等デイサービス(放デイ)は就学児(小学生〜高校生)対象
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの就学児が対象です。
学校の授業が終わったあとや、長期休暇中に利用できる通所サービスで、幅広い年齢の子どもが利用します。
18歳の年度末まで利用できる点が、児童発達支援との大きな違いです。

【一覧表】児童発達支援と放デイの違いを5つのポイントで比較
児童発達支援と放デイには、対象年齢だけでなく目的や利用時間、料金などにも違いがあります。
それぞれの特徴を理解しておくことで、子どもに合った支援を提供でき、ご家族からの相談にも的確に応じられるようになります。
以下の表で2つのサービスの違いをポイントごとに整理しましょう。
| 項目 | 児童発達支援 (略称:児発) | 放課後等デイサービス (略称:放デイ) |
|---|---|---|
| 目的 | 就学に向けた身辺自立や、読み書き、集団行動への適応など。 | 宿題支援や人間関係づくり、社会性・自立支援など |
| 対象年齢 | 未就学児(おおむね0〜6歳) | 就学児(小学生〜高校生) |
| 利用時間 | 日中または降園後 | 放課後、休日 |
| 料金 | 3〜5歳は実質無料 (幼児・保育無償化制度の対象) | 1割負担(上限〜37,200円/月) |
| 法律 | 児童福祉法 第6条の2の2項 | 児童福祉法 第6条の2の3項(厚生労働省) |
児童発達支援は幼児教育・保育無償化制度(こども家庭庁)の対象となっており、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、利用者負担が無償化されます。
また、0〜2歳児でも住民税非課税世帯の場合は無償化の対象です。
一方、放デイは無償化の対象外で、原則1割負担となっています。
所得区分に応じて上限額(〜37,200円)が設定されています。
参考:厚生労働省 障害者福祉:障害児の利用者負担
また、どちらのサービスもおやつ代やイベント参加費などの実費がかかる場合があります。
施設によって料金設定が異なるため、保護者の方に説明できるようにしておくことが大切です。
目的や役割の違いは?それぞれのサービス内容について
児童発達支援と放デイでは、サービス内容に目的や役割の違いがあります。
発達や成長に応じた療育を提供するためにも、しっかりと違いを理解しておきましょう。
児童発達支援:早期療育で「これから」の土台をつくる
就学前に行われる児童発達支援では、小学校生活に向けた基礎づくりが主な目的です。
読み書きや数の理解といった学習面の準備に加えて、排泄面や着替えなどの身辺自立、集団行動への適応など、生活全体を通した早期療育を行います。
活動は遊びや日常動作の中で進められます。感覚や手先を使った制作活動、ことばのやりとりを促す遊びなど、子どもの興味を活かした支援が中心です。
こうした取り組みを通して「できた!」という体験を積み重ね、自己肯定感や意欲を育てます。
また、保育士や児童指導員に加えて、言語聴覚士・作業療法士などの専門職が連携し、発達の総合的なサポートを行います。
児童発達支援で整えたこの“基礎力”が、就学後の安心した学校生活や社会参加の土台となります。

放課後等デイサービス:学校生活と社会生活を「つなぐ」役割
学校生活では学習だけでなく、集団での過ごし方や社会で生きるために必要な、周りに合わせるスキルなどについても学びます。
しかし、集団生活の中では一人ひとりの特性に合わせた丁寧なサポートが難しく、環境の変化や人間関係などに苦手さを感じる子も少なくありません。
放デイでは、そうした学校でサポートしきれない部分を個別にフォローすることができます。
たとえば、対人関係の練習や感情コントロールの支援、生活リズムの安定、学習面でのつまずきへのサポートなど、子どもの課題に合わせたきめ細かな支援を行います。
このように放デイでは、学校生活で培った力を社会生活につなげるための中間的なステップとしての役割を担っています。
働くスタッフ向け|仕事内容や求められる資格の違い
児童発達支援と放デイはどちらも子どもの成長を支える福祉サービスであり、活かせる資格は基本的に共通しています。
ただし、対象年齢や支援の目的によって、日々の関わり方や重視されるスキルには少しずつ違いがあります。
ここでは、共通点と違いを整理しながら、現場で求められる役割や資格について見ていきましょう。
仕事内容の共通点と違い
作成する書類や保護者対応など、おおまかな業務に違いはありませんが、サービス内容には少し違いがあります。
共通点と違いについて詳しく見ていきましょう。
| 業務内容 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 個別支援計画 | 就学準備を意識した個別目標設定 | 社会性・自立・学習支援を中心に設定 |
| 活動内容 | 遊び・感覚・運動・身辺自立など | 学習・SST・余暇活動・集団活動 |
| 保護者対応 | 発達相談・家庭での支援方法提案 | 学校との連携や家庭学習の共有など |
| 記録業務 | 発達段階を細かく評価・記録 | 学校生活とのつながりを意識 |
共通して「子どもの成長を支援する」という目的は同じですが、児童発達支援では基礎的な発達の促し、放デイでは学校生活や社会生活への適応支援が中心です。
どちらの現場でも記録・計画・連携は欠かせないため、観察力とチームワークが求められます。職員には、子どもの発達段階に応じて「今、どんな力を伸ばす時期なのか」を見極め、柔軟に関わる姿勢が求められます。
活かせる資格の違いについて
児童発達支援(児発)も放課後等デイサービス(放デイ)も、共通して子どもの発達支援に関わる仕事であるため、活かせる資格は多くの部分で重なります。
ただし、どの年齢・どんな課題をサポートしたいかによって、活かし方や求められる専門性が少しずつ異なります。
以下の表で、主な資格と活躍の場の違いを整理してみましょう。
| 資格名 | 資格を活かせる職場 | 得意分野・活かし方 | 特に活かせる場面 |
|---|---|---|---|
| 保育士 | 児発・放デイ | 生活支援・発達支援・保護者対応 | 生活支援・発達支援など、子どもの基礎的な育ちを支える場面で活かせる |
| 児童指導員任用資格 | 児発・放デイ | 学習支援・コミュニケーション支援 | 個別支援や学習サポートなど、子どもの成長を支える現場で活かせる |
| 教員免許 (小・中・高) | 主に放デイ | 学習支援・SST(ソーシャルスキルトレーニング) | 学齢期の支援が得意な人 |
| 作業療法士 (OT) | 児発でのニーズが高い | 運動・感覚統合・巧緻動作の支援 | 身体面・感覚面に課題がある子の支援 |
| 理学療法士 (PT) | 児発・放デイ | 姿勢・バランス・体幹トレーニング支援 | 身体発達支援に強み |
| 言語聴覚士 (ST) | 児発でのニーズが高い | 言葉・コミュニケーション支援 | 発語・理解の遅れへのアプローチ |
| 公認心理師 臨床心理士 | 児発・放デイ | 行動理解・情緒支援・保護者相談 | 心理・情緒面の支援を重視したい人 |
多くの資格は児発・放デイの両方で活かせますが、対象年齢や支援内容によって求められる専門性が異なります。
発達の基礎を支え、子どもの特性に合わせた支援をしたい人は児発、学齢期の子どもに社会性や自立を促したい人は放デイといったように、自分の資格を「どんな支援に活かしたいか」から選ぶのがおすすめです。
資格を軸に職場を選ぶことで、自分の強みを発揮できる環境で長く働くことができるでしょう。

サービス利用までの流れと選び方のポイント
児童発達支援や放デイの利用には、自治体での手続きや相談機関との連携など、いくつかのステップがあります。
職員としてこの流れを理解しておくことで、保護者への説明がスムーズになり、初回面談や契約時の対応にも自信を持てるようになります。
ここでは、サービス利用までの一般的な流れと、支援者が押さえておきたいポイントを整理します。
利用の相談から受給者証の取得までのステップ
- 相談支援事業所・自治体窓口で相談
まず、保護者は市区町村の福祉課や相談支援事業所に相談します。
職員は、地域の相談窓口や手続きの流れを把握しておくと案内がスムーズです。 - 医師や専門機関で意見書を取得
発達支援サービスの利用には、医師などの意見書が必要です。
記載内容(診断名・支援の必要性など)を理解しておくと、計画作成に役立ちます。 - 受給者証の申請・交付
自治体で受給者証を申請・交付し、サービス種別や負担額が決定します。
契約時には支援者も内容を確認できるようにしておきましょう。 - 事業所見学・面談
保護者とお子さんが施設を見学し、支援内容を説明して契約を結びます。
職員は「どんな支援ができるのか」を具体的に伝えられるよう準備しておくことが重要です。 - 利用契約・個別支援計画の作成
体験利用などを経て、双方に問題が無ければ利用契約を行います。
アセスメントを行い、課題や目標を整理して個別支援計画を作成します。
計画書の目的と構成を理解しておくことが質の高い支援へとつながります。 - 通所開始・支援スタート
作成した計画に基づき、支援を行います。
日々の様子のフィードバックを丁寧に行うことで、信頼関係と安定した利用継続につながります。

【チェックリスト】働く事業所選びで失敗しないためのポイント
転職や就職を検討するときは、求人票の条件だけでなく、実際の現場の雰囲気や支援方針を確認することが大切です。事業所を見学・面接するときに注目したいポイントをチェックリストとしてまとめました。
働く側として自分に合った環境を見極める参考にしてください。
| チェック項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 支援内容 | 自施設の特色を明確にし、支援方針やプログラムの説明が具体的か |
| 活動内容 | 日課やプログラム内容が具体的で、職員が子どもと関わる姿がイメージできるか |
| 職場の雰囲気 | スタッフ同士の声がけ・表情などから、職場の雰囲気やチームワークが伝わるか |
| 職員体制 | 有資格者の割合やスタッフの数、職員の雰囲気などを確認 |
| 安全面 | 室内の設備など、安全に配慮された環境となっているか |
| 教育・研修体制 | 新人研修やOJTなど、入社後に学べる仕組みがあるか |
支援の質は、職場の雰囲気やチームの文化にも大きく影響します。
「どんな支援をしたいか」に加えて、「どんな環境で働きたいか」を意識して選ぶことで、長く安心して働ける職場と出会いやすくなります。
気になる点は面接や見学で質問し、現場の雰囲気を自分の目で確かめることが大切です。
児童発達支援と放デイの違いに関するよくある質問FAQ
まとめ
児童発達支援と放課後等デイサービス(放デイ)には、対象年齢のほか、目的やサービス内容に違いがあります。
児童発達支援では未就学児童を対象に、発達支援や生活習慣の形成を中心に療育を行い、放デイでは小学生から高校生を対象に、学習支援や社会生活で必要なスキルを育み、学校と社会をつなげる中間的なサポートの役割を担います。
活かせる資格に大きな違いはなく、どのような支援をしたいかから施設選びを行うのがおすすめです。
ケア人材バンクでは、児童発達支援管理責任者(児発管)をはじめ、児童福祉分野で働く方向けの役立つ記事を掲載しています。
児発管向けの転職支援サービスも完全無料で行っていますので、ぜひご登録のうえ転職エージェントにご相談ください。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。