「ケアマネ試験に挑みたいけど、仕事をしながら合格できるのかな?」と考えている方もいるのではないでしょうか?
ここでは、ケアマネ試験の過去の合格率や偏差値などの傾向を知り、効率よく合格するためにするべきことと、ケアマネの受講要件や今後の動向などを詳しく解説します。
目次
ケアマネ試験が「難しい」と言われる5つの理由
合格率をみるとケアマネ試験は「難しい」と思われているのではないでしょうか。
ここでは、ケアマネ試験がなぜ「難しい」と言われているのか、理由をご説明します。
受験資格を得るまでが大変
ケアマネは、専門の学校を卒業したら受験資格が得られるというものではありません。
詳しくは、後ほどの記事でご紹介していますが、国家資格を保有し、相談援助業務の経験が必要であったりと、受験資格を得るまでが大変なことも、ケアマネ試験のハードルを上げている要因の一つです。
相談援助業務を行っている職員は、職場の中でも限られていることもあり、実務経験を得ることが難しい現状があります。
仕事と勉強の両立が難しい
ケアマネを受験する人のほとんどは、働きながらの受験です。
そのため、仕事、育児や家事の合間に勉強時間を確保する必要があり、十分に勉強できないまま受験しなければならない状況があります。
その一方で、以下の例のように仕事と両立することで合格に繋がったという話も聞きます。
- 介護施設等で宿直をしている人は、宿直中に勉強して合格した
- 職場の同僚で一緒に受験する人がいたので頑張ることができた
- 職場でケアマネ受験向けの勉強会が定期的に開催されていたため、モチベーションが上がり合格した
このように、仕事と勉強の両立が難しいと言われていますが、働く環境によっては、仕事をしていることがプラスに働く場合もあります。
幅広い知識が求められれる
ケアマネは、介護保険制度のことだけ勉強していたらよいと思われがちですが、以下のようなことも勉強する必要があり、幅広い内容が問われます。
- 高齢者の身体や心のこと
- 成年後見制度や生活保護制度等の介護保険制度以外の制度のこと
実務経験の中で培った知識であれば、サクサクと勉強が進みますが、聞き慣れない専門用語や言葉もたくさん出てきます。
それらを一つ一つ理解しながら進めていく必要があり、多くの知識を習得しなくてはならないことも、ケアマネ試験が難しいと言われている点です。
介護保険制度は、3年に1度改正がある
ケアマネの基本となる介護保険制度は、3年に1度制度改正があります。
そのため、試験を受ける際に、昨年までは、〇〇だった制度が、翌年受験のときには△△に変わっている、ということがあります。
テキストや問題集を受験する年に合ったものを使用しなければ、古い知識のまま試験を受けてしまうことがあるため、注意が必要です。
昨年、試験に落ちたから今年再受験しよう、とするときはどの部分が変わったかを確認する必要があります。
常に知識を最新の情報に変えておくことで、試験対策に繋がります。
出題方法が特徴的、分野ごとに合格基準がある
ケアマネの出題方法は、五肢複択方式です。
五肢複択方式とは、5つの選択肢から複数の正解を選ぶ方式です。
選択肢の中から、答えを1つでも間違えると不正解になってしまうため、介護福祉士のように、5択から1つ選ぶ試験より難しくなります。
また、ケアマネ試験は、分野ごとに70%以上の正答が必要です。
そのため、苦手な分野もしっかりと知識を習得する必要があります。仕事内容と重なっている分野の点数は伸ばせそうですが、重なっていない分野もしっかりと勉強する必要があることもケアマネ試験が難しいと言われている理由です。
ちなみに、ケアマネ試験は、毎年難易度によって、明確な合格点が分からないため、自己採点をしても、実際に合格しているかは、合格発表まで分かりません。
ケアマネ試験の合格率と偏差値から見る最新の難易度
ケアマネ試験の過去から現在までの合格率、他の資格と比較した偏差値はどのぐらいなのかを紹介します。
ケアマネ試験の合格率はどのぐらい?
第27回(令和6年度)に実施された試験では、合格率は32.1%でした。
過去の合格率は以下の通りです。
| 実施年度 | 合格率 | 実施年度 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第1回(平成10年度) | 44.1% | 第16回(平成25年度) | 15.5% |
| 第2回(平成11年度) | 41.2% | 第17回(平成26年度) | 19.2% |
| 第3回(平成12年度) | 34.2% | 第18回(平成27年度) | 15.6% |
| 第4回(平成13年度) | 35.1% | 第19回(平成28年度) | 13.1% |
| 第5回(平成14年度) | 30.7% | 第20回(平成29年度) | 21.5% |
| 第6回(平成15年度) | 30.7% | 第21回(平成30年度) | 10.1% |
| 第7回(平成16年度) | 30.3% | 第22回(令和元年度) | 19.5% |
| 第8回(平成17年度) | 25.6% | 第23回(令和2年度) | 17.7% |
| 第9回(平成18年度) | 20.5% | 第24回(令和3年度) | 23.3% |
| 第10回(平成19年度) | 22.8% | 第25回(令和4年度) | 19.0% |
| 第11回(平成20年度) | 21.8% | 第26回(令和5年度) | 21.0% |
| 第12回(平成21年度) | 23.6% | 第27回(令和6年度) | 32.1% |
| 第13回(平成22年度) | 20.5% | ||
| 第14回(平成23年度) | 15.3% | ||
| 第15回(平成24年度) | 19.0% |
出典:介護支援専門員実務研修試験の実施状況について|厚生労働省
受験者数は、平成30年度から受験資格が厳しくなったことが影響し、平成29年度は131,560人だったのが 平成30年度は49,332人と減少。そこから近年まで55,000人前後で推移しています。
近年、合格率が上がってきている背景には、ケアマネの深刻な人材不足が影響しています。
受験資格が厳しくなった上、ケアマネになると処遇改善手当が支給されなくなり、介護職より給料が下がるので、ケアマネを希望しない人も増えてきていると聞きます。
また、ケアマネ資格ができたときにケアマネを取得しているケアマネが高齢化してきており、新たな担い手が必要になってきています。
これらの理由から、合格率が上昇していると言われています。
【徹底比較】他の介護・福祉系資格と難易度はどう違う?
介護福祉士や社会福祉士といった関連資格と比較し、ケアマネ試験の立ち位置を明確にします。「介護福祉士の次はケアマネを目指せる?」「社会福祉士とどっちが難しい?」といった具体的な疑問を持つユーザーに役立つ情報を提供します。
社会福祉士、介護福祉士、ケアマネの違いとは?
| ケアマネ (介護支援専門員) | 社会福祉士 | 介護福祉士 | |
|---|---|---|---|
| 受験資格 | ・国家資格を有し、かつ業務経験を5年以上(900日以上) ・相談援助業務に5年以上(900日以上)従事した者 | ・大学で指定科目を修めて卒業 ・短大等卒業+実務経験 ・一般大学卒業+養成施設1年 | ・介護業務の実務経験3年以上(540日以上)+「実務者研修」修了 ・介護福祉士養成施設を卒業 ・指定された福祉系高校を卒業 |
| 業務内容 | ケアプランの作成や調整、相談 | 幅広い福祉の相談、虐待対応、支援 | 身体介護、生活援助 |
| 管轄 | 都道府県実施 (試験は共通問題) | 国家資格 | 国家資格 |
| 仕事場所 | ・居宅介護支援事業所 ・介護施設 等 | ・福祉事務所 ・病院 ・介護施設 ・地域包括支援センター 等 | ・介護施設 ・障がい者施設 ・訪問介護 ・病院 等 |
福祉の資格で代表的なものに、ケアマネ、社会福祉士、介護福祉士があります。
ケアマネの受験資格を得るための1番多いルートが介護福祉士の資格を取得し、ケアマネ試験に臨むことです。
ケアマネの受験資格である国家資格は介護福祉士、社会福祉士のみならず、看護師、管理栄養士、理学療法士、柔道整復師など幅広い国家資格に対応しています。
ただ、圧倒的に多いのが「介護福祉士」となっています。
ケアマネは高齢者のプランを立案することから、介護系の資格を持った方が目指しやすいと考えられています。
また、介護は夜勤などの変則勤務もあることから、長く働いていきたいと考えている中で候補に上がってくるのが「ケアマネ資格」となります。
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員の難易度
| ケアマネ (介護支援専門員) | 社会福祉士 | 介護福祉士 | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 第23回:17.7% 第24回:23.3% 第25回:19.0% 第26回:21.0% 第27回:32.1% ※直近の合格率 20%~30%代 | 第33回:29.3% 第34回:31.1% 第35回:44.2% 第36回:58.1% 第37回:56.3% ※直近の合格率 40%~50%代 | 第33回:71.0% 第34回:72.3% 第35回:84.3% 第36回:82.8% 第37回:78.3% ※直近の合格率 70%~80%代 |
| 試験時期 | 例年10月 (年1回) | 例年2月初旬 (年1回) | 例年1月末 (年1回) |
出典元:第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について|厚生労働省
第37回社会福祉士国家試験合格発表について 参考欄|厚生労働省
第37回介護福祉士国家試験合格発表について 参考欄|厚生労働省
年度によって合格率は変わってきますが、上記が目安の合格率です。
介護福祉士は、受験要件を満たし、普段の実務経験から知識を得ながらコツコツ勉強すると、仕事をしながらでも取りやすい資格となっています。
この合格率だけを見ると、ケアマネが1番合格率が低く難易度が高いと感じるかと思います。
しかし、受験要件が、社会福祉士では、必ず学校を卒業(実習あり)するか、養成施設で1年は勉強する必要があります。
そこを卒業してようやく受験ができますが、高齢者、障がい者、児童、生活保護など幅広い分野での知識が求められるため、受験の勉強は欠かせません。
ケアマネよりも出題範囲が広い上に、実務経験のみでは受験資格が得られないため、社会福祉士の方が難易度が高めだと言う方もいます。
合格に必要な勉強時間とおすすめの勉強法
合格するために必要な総勉強時間の目安(例:100~200時間)を提示し、学習計画のイメージを持たせます。
「独学」「通信講座」「通学講座」それぞれのメリット・デメリットを解説し、自分にあった勉強法の選択をサポートします。
おすすめのテキストや問題集に触れると、より具体的なアクションに繋がります。
合格に必要な勉強時間はどのくらいか?
ケアマネ試験に合格するために必要な時間の目安は、一般的には100〜200時間だとされています。
働きながら100〜200時間の勉強の時間を確保することはとても大変です。
しかし、これはあくまでも目安であり、自分に合った勉強方法を試みることで、勉強時間を短縮できたり、効率的に無理なく勉強することもできます。
机に向かって教科書を広げていることだけが「勉強」ではありません。
普段の業務や仕事の中でケアマネの知識を得るために学ぶべきことがたくさんあります。
介護や看護で働いている方などは、身近で分からないことがあったら積極的に調べたり、先輩や他の職員に質問する姿勢がケアマネ試験合格の近道となります。
おすすめの学習計画
まずは、「独学」「通信講座」「通学講座」のメリット・デメリットを知り、どの方法で学ぶかを選びます。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 独学 | ・金銭面で安い。 ・本屋などで、自分にあったテキストや参考書を選べる。 ・自分のペースで勉強できる。 ・YouTubeで試験対策のchも複数あり、分からない問題のみ視聴可能 | ・たくさんある中の参考書でどれを選んで良いか分からない。 ・学習計画をしっかりと立てる必要がある。 |
| 通信講座 | ・通学講座よりは安く、勉強は比較的自分のペースでできる。 ・不合格の場合の保証がついている通信講座もある。 ・分かりやすくまとめられたテキストや参考書や過去問がそろっており、通信講座にだけ絞って いたら他の参考書を購入する必要がない。 | ・予想問題など、期限までに提出する必要がある(強制力はない) ・送られてきた参考書をどのようなペースでおこなっていくかの配分を考える必要がある。 ・分からない問題の質問はできるが、返答までに時間がかかる場合がある。 |
| 通学講座 | ・時間と場所が定められているので、強制的に勉強する環境が整う ・ケアマネの試験対策に十分な参考書が用意されている。 ・同じ通学仲間と共に高めあっていくことができる。 ・分からない箇所は、すぐに質問し、理解ができる。 | ・金銭的に高い。別途交通費もかか る。 ・通学時間が決められており、変則勤務などの場合、両立が難しい場合がある。 |
次に学習計画を立てます。
「通学講座」の場合は、通学しながら予習や復習をし、理解を深めていくことが大切です。
また、試験に出やすい大切なポイントも教えてくれるので、しっかりメモを取りましょう。
「独学」「通信講座」の場合は、勉強時間の確保が必要です。どのように勉強していくか効率の良い方法で学んでいくことが大切です。
以下は、おすすめの勉強方法です。
朝に勉強時間を確保する
朝は、頭が一番働きます。
いつもより1時間早く起きて、朝食を食べゆったりとした気持ちで試験勉強することがおすすめです。
試験勉強に重要なのは、ながら勉強をしないことです。
ケアマネ試験は難しい用語や複雑な介護保険システムを覚える必要があります。
その時はやはり「集中」し覚えていくことが大切です。
過去問に取り組む
過去問は、過去の問題の傾向を知ることや、どのような形式で試験が出されるのかを知ることができます。
過去問を解かず合格することは難しいです。最低でも過去3〜5年分を繰り返し解いていくことで、問題に慣れることができます。
そして、過去問で同じ箇所を間違える場合は、その分野は「苦手」と捉え、テキストで確認し、知識を深める必要があります。
また、分からない用語などが出てきた場合も、用語を調べる必要があります。
隙間時間の活用
休憩時間や、通勤時間、夜勤の時間を有効に活用しましょう。
持ち運びしやすい一問一答などを常備し、合間に確認や問題に取り組むことで知識を深めることができます。
4月から始めた場合のおすすめ学習計画例
| 4月 | 過去問直近5年分を取り組み、過去問から苦手な分野を理解します。 時間を気にせず、1問1問丁寧に解いていき、問題の意味が分からない箇所、用語が分からない箇所、いまいち理解できていない箇所などには印をつけます。 |
| 5月 | 取り組んだ過去問から、理解できていない用語の確認や、テキストや問題の解説を活用し、知識を深めます。 文字で覚えるだけではなく、図や表を活用すると良いでしょう。 |
| 6月 | 空き時間などに1問1答を繰り返し解いていきます。 何度も間違える問題はチェックし、テキストでを見直すなど確認を行います。 |
| 7月 | この段階で、何度覚えようとしても覚えきれない箇所が出てくる場合もあります。 また、得意・不得意も分かってくるので、覚えられない箇所は、ノートに転記し、理解を深めましょう。 自分だけのオリジナルノートはすぐに確認できるように持ち歩きましょう。 |
| 8月 | |
| 9月 | 過去問や予想問題などを時間を測って実際に解いてみましょう。 分からない問題は解説やテキストで確認しましょう。 |
| 10月 | 最終確認です。 苦手な箇所の復習、過去問をしっかり解いて自信をつけましょう。 |
おすすめのテキスト・問題集
【おすすめポイント】
- 過去5回分の試験問題を全問収載してるので、過去問対策が出来る。
- 明解な短文解説で正誤の根拠をしっかり理解できる。
- 問題ごとの「ポイント」で知識の基盤を強化できる。
【おすすめポイント】
- 複雑な制度のしくみや専門用語、医療知識など、覚えるべきポイントを図や表を交えて押さえて、整理できる。
- 「重要事項・頻出事項」を確実に記憶・理解を深めることができる。
- ケアマネジャー試験の全体像をつかんで覚えることができる。
【おすすめポイント】
- 10年分の試験問題が分析されている。
- 「改正」「注目」マークで試験にでやすい問題などわかりやすく表記
- 解説文は付録の赤シートを使って穴埋め問題としても活用できる
- イラスト・図表を用いた「重要ポイントまとめてCHECK!!」でポイントを整理し、理解 を深めることができる
【おすすめポイント】
- ・独学でも受かるポイントが書かれている。
- ・テキストと問題集が一体化されているので、知識の定着と問題演習が1冊でできる。
- ・必修テーマが見開き完結でまとまり、テンポよく学べ、口コミでも「見やすい」と評価が高い
- 3回分の「予想模擬試験」を掲載しているので、腕試しもできる。
ケアマネになるには?受験資格の要件と今後の動向
そもそも誰が受験でき合格するのか、という基本的な情報を解説します。
定められた国家資格(介護福祉士、社会福祉士、看護師など)の保有と、それに基づく実務経験が必要な点を分かりやすく説明します。
今後の制度改正の可能性など、将来的な展望にも触れ、受験を検討しているユーザーの不安を解消します。
ケアマネ試験を受験するのに必要な国家資格
ケアマネ試験を受験するのに必要な国家資格は以下の通りです。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 視能訓練士
- 義肢装具士
- 歯科衛生士
- 言語聴覚士
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
- きゅう師
- 柔道整復師
- 栄養士(管理栄養士)
- 精神保健福祉士
※国家資格を有していなくても、相談援助業務に従事し、経験のある方は受験できます。生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員などです
ケアマネ試験を受験するのに必要な実務経験
ケアマネ試験を受験するためには、以下の2つの条件を両方満たすことが求められます。
保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務及び一定の相談援助業務の実際に従事した以下の実務経験期間が必要です。
- 通算5年以上の実務経験期間
- 通算900日以上の実務従事日数
【国家資格等に基づく業務を実務経験として受験する場合】
国家資格等を持ち、その資格等に基づく業務を受験資格として申し込む場合、実務経験は、その業務で勤務し始めた年月日ではなく、国家資格等の登録された日以降その業務についた初日となります。受験資格要件である日数、年数を計算される際、不足がないか確認してください。
出典:令和7年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験受験要項
ケアマネの今後の制度改正と将来的な展望
処遇改善加算を検討
今後、高齢化を背景にケアマネの需要はますます高まると考えられています。しかし、責任が大きいのに給料が少ないのが現実で、深刻な人材不足となっています。
処遇改善加算など、その他の加算要件を見直し、賃金を上げることが課題となっています。
業務の効率化
ケアマネの仕事は行政や事業所、地域住民、ご家族、利用者様と幅広く連携し、対応していきます。
そのため、何人もの方を1人で担っていくには限界があります。今後はITを活用しながら業務の効率化を図りつつ、質を向上していくことが望まれています。
法定研修の見直し
ケアマネジャーの法定研修は5年に1度実施されています。そのため、普段の業務を行いつつ、研修を受けるとなるとかなりの負担となっています。
今後は、更新制廃止を含めた見直しが議論されています。
将来的な展望
ケアマネジャーは、他職種と連携しあい、利用者様に寄り添うことができるやりがいのある仕事です。しかし、問題も複雑化しており、ケアプラン通りに支援を実施できないのも事実です。
昨年のケアマネの試験の合格率が30%を超えていることから、ケアマネの人材不足が見えます。今後は、ケアマネの質を維持しつつ、人材確保や業務の効率化に力を入れていくと考えられています。
まとめ
ケアマネの試験は、しっかり対策し勉強したら受かるようになっています。
自分にあった方法を見つけ、しっかりと勉強していくことと、試験の内容や傾向を押さえ、本番に力を発揮することが大切です。
普段の業務の中でも、ケアマネ試験に役立つことがたくさんあります。
仕事の中で分からないことは調べるか、先輩に聞きながら知識を深めていくことで、よりケアマネの試験勉強をスムーズに行えるでしょう。
ケアマネ試験では、介護保険や医療、福祉の幅広い問題が出題されます。そのため、「施設での経験はあるけど、在宅での仕事も知っていきたい」「施設で、看護師からもっと医療について教えてもらいたい」など、知識を深めたいし、もっと経験もしたい!と転職を考えている方は、ぜひ一度ケア人材バンクにご相談ください。
「一人ではどのように探したらいいかわからない」「何を基準に選んだらいいかわからない」という人は、専任アドバイザーがサポートします。
ケアマネ試験に合格し、「ケアマネとして一歩を踏み出したい」という方にもおすすめです。
過去の経験からの情報が豊富にあるため、自身にマッチした職場が見つけやすくなります。
よくある質問FAQ
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。
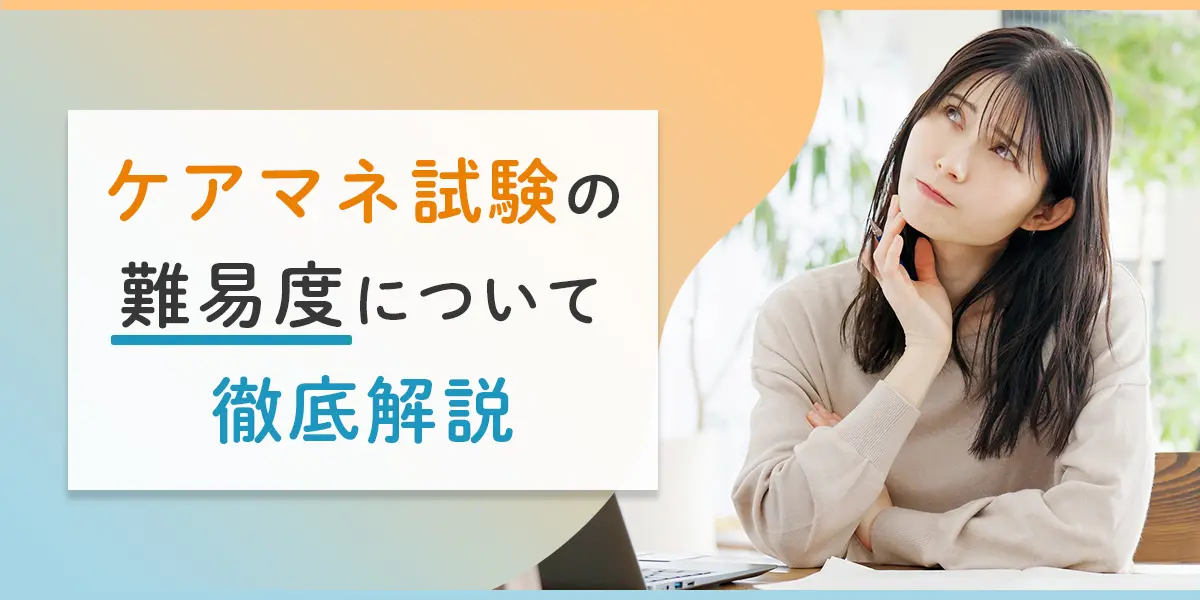


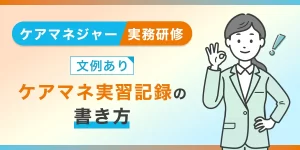
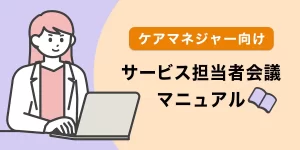


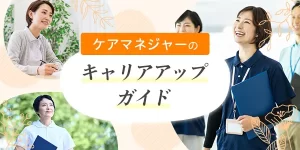
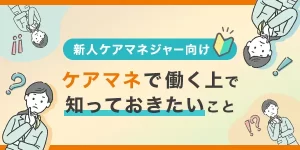
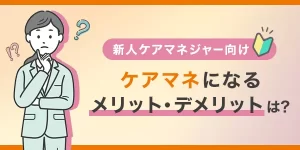

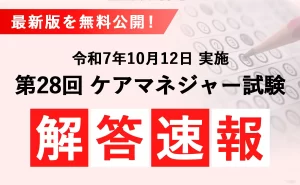

【2025年度ケアマネ試験 受験者の方】
姉妹サイト「ウェルミージョブ」なら、ケアマネ試験の自己採点ツールを提供中!
利用者の平均点集計機能付きで、今年の試験の難易度も確認できます。