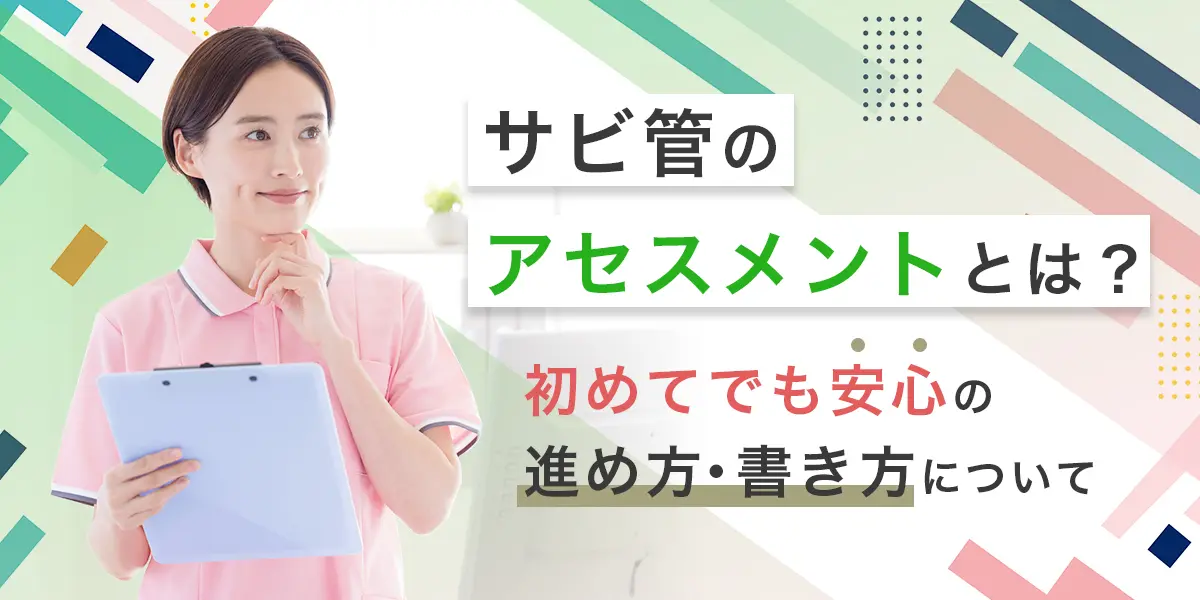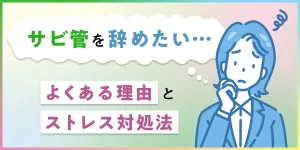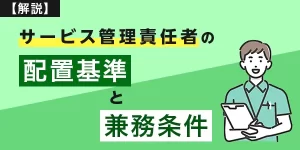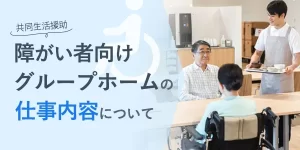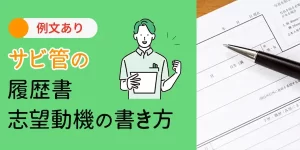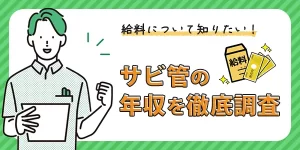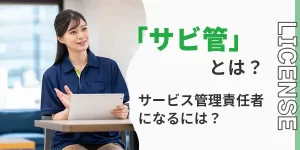サビ管としてアセスメントを担当していると、つい同じ質問を繰り返してしまい、「本当に利用者様のことを理解できているのだろうか」と不安になることはありませんか?
アセスメントは、慣れてくるとスムーズに行うことができますが、逆に「機械的になってしまっている」「周囲から”誰にでもできるじゃないか”と思われているのでは」と、自分を責めてしまうこともありますよね。
この記事では、サビ管としてアセスメントの本質を整理し、次の面談から実践できる具体的な視点や質問の工夫をお伝えします。
目次
サビ管の要!アセスメントの目的と個別支援計画における重要性
アセスメントスキルは、サビ管の要といっても過言ではありません。
アセスメントに力を入れられるかどうかで、支援の質は大きく左右されます。
ここでは、アセスメントの目的や役割、個別支援計画との関係性について解説します。
アセスメントが支援の出発点である理由
アセスメントは、利用者の希望や困りごとを把握し、支援の方向性を決める「出発点」です。
利用者様をよく理解せずに支援を始めると、ご本人に合わない目標設定や取り組みになり、成果が出にくくなってしまいます。
だからこそ、最初のアセスメントで「何を大切にしている人なのか」「どんな生活を送りたいのか」を丁寧に聞き出すことが欠かせません。
特に福祉の現場では、利用者様自身の言葉が計画の軸になります。
医師の診断やご家族の意見も参考になりますが、「ご本人の希望」が出発点であることを忘れてはいけません。
利用者様自身の声を拾いきれなかった支援計画は、実行段階でつまずきやすいのです
個別支援計画の質を左右するアセスメントの役割
個別支援計画は「アセスメントの質」で決まるといって良いでしょう。
表面的なヒアリングでは、どうしても「誰にでも当てはまるような計画」になってしまいがちです。
逆に、生活の細部まで理解できれば、より具体的で実行可能な支援方針を立てられます。
例えば「就労を目指す」といっても、以下のような背景によって意味が大きく変わります。
- 「家族の希望で就労したい」
- 「自分の収入で好きなものを買いたい」
- 「人との交流のために働きたい」
この違いを把握しているかどうかで、支援のアプローチはまったく変わります。
根拠のある支援につなげるための情報収集
アセスメントで集める情報は、単なる「記録のため」ではなく、支援の根拠を示すためのものです。
「なぜこの支援を行うのか?」を説明できるようにするため、生活歴、健康状態、家族関係、就労経験、希望や不安といった情報を体系的に整理する必要があります。
サビ管の中には、「ご本人が希望していない就労支援を強調してしまい、後で利用者様のモチベーションが下がった」という経験をした人もいるようです。
それは、ご本人の生活背景を十分に聞き取れていなかったのが原因でした。
だからこそ、支援の根拠を裏付ける情報を意識して集めることが重要なのです。
アセスメントの基本的な流れ【5つのステップで解説】
ここからは、アセスメントの基本的な流れについて解説します。
この流れは、どの自治体でも、どの事業所でも基本となっているものです。
事前準備(情報収集と仮説立て)
支援記録や過去の計画書を確認し、事前に「どんなニーズがあるか」「どの部分を深掘りすべきか」を整理しておくと、面談がスムーズになります。
例えば以下のように、事前に情報記録を確認しておくことで、仮説が立てられます。
仮説があることで、面談中に適切な質問を投げかけやすくなります。
【情報収集】
「通所の遅刻が多い人」
↓
【仮説】
「体調が不安定なのか」
「交通手段に問題があるのか」
インテーク面接(信頼関係の構築)
最初の面談は、利用者様が安心して話せる雰囲気をつくることが信頼関係構築の第一歩です。「今日はどんなことを話したいですか?」とご本人主導で始めるだけでも印象が変わります。
また、支援者が一方的に「聞きたいこと」を並べるのではなく、世間話や趣味の話から入ることも効果的です。
信頼関係が構築できれば、核心的な質問にも本音で答えてもらえる可能性が高まります。
アセスメント面談の実施(ご本人・ご家族へのヒアリング)
利用者様だけでなく、ご家族や関係者からも情報を集めると、生活の全体像が見えやすくなります。例えば以下のような点を補完的に得られます。
- 「ご本人は言えないけど家族が把握していること」
- 「支援者から見える行動の特徴」
例えば、利用者様自身は「就職したい」と話していても、ご家族は「生活リズムが整わず心配している」と感じている場合もあります。
両方の視点を把握してこそ、現実的な支援方針を立てられます。
情報の整理と分析(ニーズの明確化)
面談内容をただ羅列するのではなく、「ご本人の希望」「課題」「必要な支援」の3点に整理して考えると、自然とニーズが浮き上がってきます。
例えば、以下のように整理を行うことで、支援計画が実際の行動に直結しやすくなります。
| ご本人の希望 | パートで週3日働きたい |
| 課題 | 朝の起床が不安定、通勤に不安あり |
| 必要な支援 | 生活リズムの改善、通勤練習のサポート |
アセスメントシートへの記入
整理した情報をアセスメントシートにまとめます。
このとき、単なる事実の羅列ではなく、「なぜそう考えるのか」という理由を簡単に書き添えると、計画書の根拠として一層使いやすくなります。
例えば、以下のように理由を記入することで、支援者間での共有もスムーズになります。
- 「〇〇さんは週3日の就労を希望しているが、朝の起床が安定せず遅刻が多いため、生活リズムの改善支援が必要と考えられる」
- 「〇〇さんは、他の利用者とのコミュニケーションで度々トラブルになる。ご本人も『ついカッとなってしまう』と話しており、アンガーマネジメントの訓練が必要と考えられる」
- 「〇〇さんは、給料を計画的に使うことが苦手で、月末にはいつもお金がなくなってしまう。そのため、金銭管理の練習や、必要に応じて相談できる体制を整えることが必要と考えられる」
ニーズを引き出す!アセスメントの質問項目とヒアリングのコツ
ここからは、利用者様のニーズを引き出す上で効果的な質問項目やヒアリングのコツをご紹介します。
どれも無理なく、少し意識すればできることばかりですので、ぜひお試しください。
利用者様がイメージしやすい質問に置き換える
たとえば「普段の生活の中で困っていることはありますか?」と聞いても答えにくいことがあります。
以下の質問のように、具体的な場面を想定した質問に置き換えることで、本音を引き出しやすいです。
- 「朝起きるのは大変ですか?」
- 「通所の準備にどのくらい時間がかかりますか?」
見通しの立てやすい質問をする
「将来の希望は?」と聞かれると漠然としすぎて答えられない人も多いです。
以下の質問のように、短期的・具体的な視点で聞くと答えやすくなります。
- 「半年後にどんな生活をしていたいですか?」
- 「今の生活で続けたいことはありますか?」
答え方を複数用意する
面談中に利用者様がなかなか言葉にできず沈黙が続くケースもあります。
その時に「無理に答えなくても大丈夫です。メモや絵で表してもらえますか?」などと声をかけることで、安心して気持ちを伝えてくれるでしょう。
方法を柔軟にすることで、より正確な情報を得ることができます。
アセスメントで陥りがちな失敗例と対策
ここからは、アセスメントで陥りがちな失敗とその対策を解説します。
質問が多すぎて面談が”尋問”になってしまう
ある利用者様のアセスメントでの失敗事例を共有します。
アセスメントに慣れない頃は「聞き漏らしてはいけない」と思い、準備した質問をすべて消化しようとしていました。
その結果、面談がまるで“尋問”のようになり、利用者様が疲れてしまったことがあります。
利用者様から「今日は質問ばかりでしんどい」と率直に言われ、ハッとした経験もありました。
この失敗から「アセスメントは会話であって調査ではない」ということを学びました。
質問項目をチェックすること自体は大切ですが、それ以上に「相手が話したいことを自然に引き出す雰囲気づくり」の方が重要です。
今は「沈黙も会話の一部」と考え、あえて余白を作ることで、ご本人が自分の言葉で話し出す場面が増えています。
ご本人よりも「ご家族の意向」を優先してしまう
ある利用者様のアセスメントで、ご家族からの要望ばかりを重視してしまったケースをご紹介します。
「安定した仕事に就いてほしい」「できるだけ施設に通っていてほしい」など、ご家族の思いをそのまま計画に反映させてしまったため、後から、利用者様自身が「本当は在宅でできる仕事に挑戦したかった」と不満を漏らされ、大きな信頼の揺らぎにつながりました。
この経験から「ご本人が主体であること」を見失ってはいけないということを痛感しました。
もちろんご家族の意見は大切ですが、それはあくまで参考であり、最終的な意思決定は利用者様自身の希望を基盤にするべきです。
「まずご本人に確認する」ことを徹底し、たとえご家族との意見にズレがあっても、両者の橋渡しをする、という意識が大切です。
記録に時間をかけすぎて現場で活かせない
アセスメントの記録を丁寧に残そうとするあまり、膨大な情報を書き込みすぎてしまった事例もあります。
面談の録音を文字起こしに近い形で記録し、結果として「読むのに時間がかかりすぎる」「支援の現場に落とし込めない」という失敗につながりました。
アセスメント記録は「網羅する」よりも「支援に直結する情報を絞る」方が有効だということです。
「利用者様自身の強み」「困りごと」「支援の糸口」の3つに分類して簡潔に残すようにしています。記録がシンプルになると、職員間の共有もスムーズになり、「次にどう動くか」が明確になりました。
まとめ
アセスメントは、サビ管としての支援の土台を築く非常に重要なプロセスです。
単なる質問の羅列ではなく、「利用者様自身を主体とする支援」を形づくるための出発点であり、個別支援計画の質を左右します。
今回の記事では、以下の内容を整理しました。
- アセスメントの目的や重要性
- 5つの基本的な流れ
- ヒアリングで使える質問の工夫
- 陥りがちな失敗例とその対策
大切なのは、「利用者様自身の思いをどう引き出し、どう支援に結びつけていくか」を常に意識することです。
形式的な質問や過剰な記録にとらわれず、次の行動につながる情報を残すことで、現場の支援力が確実に高まります。
ケア人材バンクでは、サービス管理責任者の転職支援サービスを提供しています。
障害福祉に特化したエージェントが、あなたのキャリアを丁寧にサポートし、希望に合った職場との出会いをお手伝いします。
登録は無料ですので、キャリアの可能性を広げたい方はぜひ「ケア人材バンク」をご利用ください。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。