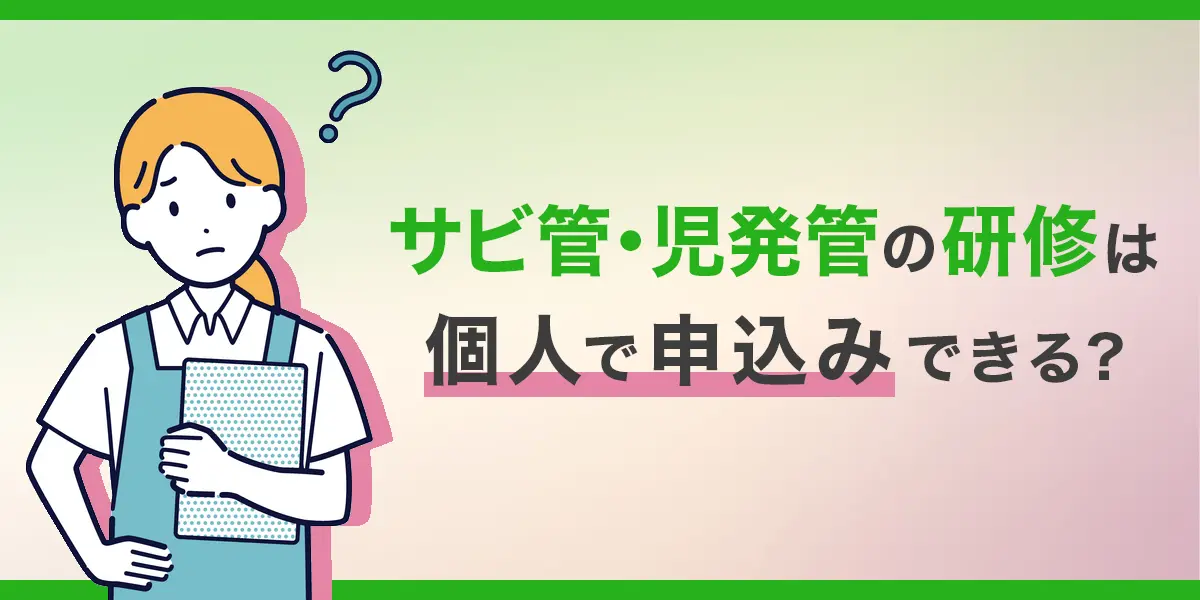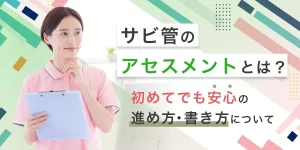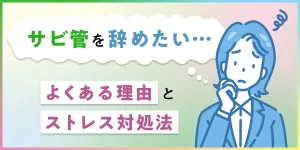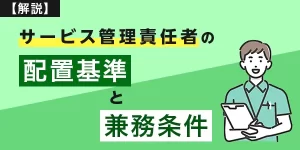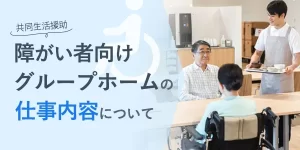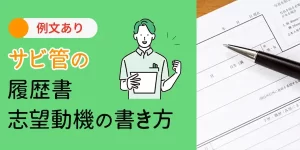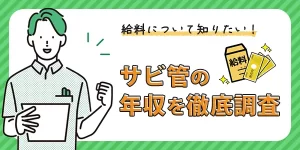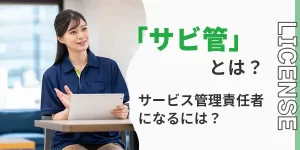目次
サビ管・児発管研修個人申し込み可能?
サビ管・児発管研修は、原則として事業所経由で申し込むケースが多いですが、個人での申し込みが可能な自治体も存在します。
ここでは、個人申し込みの可否について、自治体ごとの違いや傾向を見ていきます。
自治体によって異なる個人申込可否について
サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)研修は、基本的に事業所経由での申し込みが一般的です。
ただし、自治体や主催団体によっては、個人での申し込みができるケースもあります。
たとえば、以下のような場合「自己推薦」や「理由書の提出」などの形式で個人での申し込みが可能な自治体も一部存在します。
- これから事業所を設立する予定の方
- 現時点で推薦してくれる事業所がない方
ただし、都道府県や研修実施機関ごとにルールが異なるため、最新の募集要項や申込基準の確認は必須です。
申し込み基準変更背景について
研修制度の見直しや受講希望者の増加により、申し込み基準にも徐々に変化が見られるようになってきました。
ここでは、その背景となる要因について詳しく見ていきます。
集合研修による制限
サビ管・児発管の研修は、年々希望者が増加しています。
特に制度改正によって、「5年ごとの更新研修」が義務化されたこともあり、受講者数はさらに増加傾向にあります。
そのため、定員を上回る申し込みが集まることが通例で、多くの自治体では、以下のような制限を設けていました。
- 定員超過時に「抽選」や「選考」「先着順」方式を導入
- 複数人申し込みの際は事業所内で優先順位を決めて申し込み
- 「県内在住・勤務者」のみに限定する
そういった会場のキャパシティの問題から、「実際に働くことが決まっている人」を優先する必要がありました。
オンライン研修へ切り替わり
近年のサビ児管研修では、オンライン研修の普及により会場のキャパ問題が一定程度解消されています。
これに伴い、働く予定のある方や、キャリアアップ希望者も申し込みやすくなっています。
近年は、eラーニングやZoomなどによる事前学習、課題提出を行い、最終的なグループワークや演習のみ集合研修で行うハイブリッド型が一般的です。
オンライン部分については、定員や会場制約をほぼ受けずに受講することができます。
申し込みに地域制限を設けない研修事業者増加
オンライン研修の普及により、以前は「○○県内の事業所所属者のみ」と制限していた研修も、現在では他県からの申し込みを受け付ける事業者も少しずつ増えてきました。
原則としてその自治体内で働く(または配置予定の)事業所職員を優先し、定員に余裕があれば他府県からの申し込みも受け付けるという地域優先方式が主流となっています。
都道府県別 個人申込み可否一覧
サビ管・児発管研修の個人申し込み可否について、都道府県ごとにまとめました。
お住まいの自治体での申し込み可否を確認する際にご活用ください。
※最新情報は各自治体の公式サイトで必ずご確認ください。
作成日:2025/7/28
都道府県 | 個人申込 可否 | 詳細 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | × | 事業所の推薦が必要。 個人で直接申し込むことは原則不可。 オンライン研修は個人でも利用可。 | 北海道庁 |
| 青森県 | × | 原則事業所経由。個人申し込み不可。 | 青森県庁 |
| 岩手県 | × | 基礎研修・実践研修・更新研修ともに対面形式で事業所推薦が必要。 個人単独では基本的に申し込めない構造。 | 岩手県庁 |
| 宮城県 | ◯ | 県内実施事業者へ直接申込(社福協・東北福祉カレッジ・学研ココファン等)。 要実務経験・詳細は各事業者サイト参照。 | 宮城県庁 |
| 秋田県 | × | 自治体主催研修は事業所経由。 学研ココファン等民間オンライン研修では個人申込可(詳細は各事業者サイト参照)。https://fukushi.gakkenlx.jp/ | 秋田県庁 |
| 山形県 | ◯ | 個人申込可。 県電子申請フォームで直接申込OK。 実務経験要(OJT2年等)。 | 山形県庁 |
| 福島県 | × | 自治体主催研修は県内事業所所属者が対象(他県・個人単独不可)。 オンライン講義も混在。最新要項は県障がい福祉課サイトを参照。 | 福島県庁 |
| 茨城県 | × | 自治体指定研修は協会を通じて実施。 申込は事業所または団体単位、個人単独の申込不可。 | 茨城県庁 |
| 栃木県 | × | 自治体指定の研修は障害福祉協会等を通じて事業所単位で申込。 個人単独での申し込み不可。 | 栃木県庁 |
| 群馬県 | × | 県主催研修は「県内の事業所所属者」が対象で、所属・推薦が必要。 個人単独での申し込み不可。 | 群馬県庁 |
| 埼玉県 | × | 県指定の研修は指定事業者による実施。 電子申請+書類郵送での事業所推薦が必須。個人単独での申し込み不可 | 埼玉県庁 |
| 千葉県 | ◯ | 個人申込OK。 電子申請+必要書類郵送の両方が必要。 法人も個人も申込可、要実務経験・千葉県内勤務。 | 千葉県庁 |
| 東京都 | × | 指定研修事業者による研修を実施。 東京都または指定機関に所属し、組織からの推薦・申請が必須。個人単独での申し込みは不可。 | 東京都庁 |
| 神奈川県 | ◯ | 神奈川県社協研修センターの研修管理システムから個人ログイン・申込可能(法人推薦不要)。e‑ラーニング+集合研修で構成。 | 神奈川県庁 |
| 山梨県 | ◯ | 個人申込可。 山梨県障害者福祉協会の研修事業に個人で申込OK(県内事業所所属者優先)。 実務経験要件あり。 | 山梨県庁 |
| 長野県 | × | 自治体指定研修は県内事業所所属者対象。 フォーム使用可も「他県や個人での申込はできません」と募集要項に明記。 | 長野県庁 |
| 新潟県 | × | 電子申請可も、法人等の推薦書+返信用封筒が必要。 県内事業所所属者対象で、個人単独では申込不可。 | 新潟県庁 |
| 富山県 | × | 電子申請フォームありも、推薦書(事業所提出)が必須。 県内事業所所属対象で個人単独不可。 | 富山県庁 |
| 石川県 | × | 対象は県内事業所所属者。 要項PDFに推薦書必須と明記。個人単独申込不可。 | 石川県庁 |
| 福井県 | × | 電子申請可だが、県内事業所所属者対象で、県外や個人単独の場合は一律お断りと明記。 個人単独での申し込み不可。 | 福井県庁 |
| 岐阜県 | × | 自治体主催研修は「事業所所属 or 従事予定」対象。 申込には実務経験証明・事業所記入欄あり。 個人単独での申し込みは不可(要項PDFより) | 岐阜県庁 |
| 静岡県 | × | 個人申込についての記載なし。 | 静岡県庁 |
| 愛知県 | × | 自治体指定の研修は県内事業所所属者対象。 申込には法人事業所情報と実務経験証明の提出が必須。個人単独での申し込み不可。 | 愛知県庁 |
| 三重県 | × | 三重県社協が研修窓口を担当。 申込は「所属事業所による推薦+実務経験証明+様式提出」が必要で、個人単独申し込み不可。 | 三重県庁 |
| 滋賀県 | × | 電子申請フォームあり。「申込みは原則、法人や事業所からのみ。 個人のスキルアップのための申込みはできません」と公式案内に明記。 県内事業所所属者対象。 | 滋賀県庁 |
| 京都府 | × | 基礎・実践・更新研修はすべて「所属事業所からの推薦+実務経験要件」が前提。 個人単独申し込み不可(要項PDFより)。 | 京都府庁 |
| 大阪府 | × | 指定された障がい福祉サービス事業者からの推薦書提出が必須。 原則として法人推薦が要件で、個人単独申込は制度上不可(要項より、退職など例外時に限り個人申し込み扱いとなる)。 | 大阪府庁 |
| 兵庫県 | × | 公式Q&Aに「個人での申込みはできません」と明記あり。 原則は所属事業所経由。 新規開設予定の場合は予定事業所名の記載で例外的に申込み可能。 | 兵庫県庁 |
| 奈良県 | × | 要項に「申し込みの際、事業所番号入力が必要」かつ「県外所属者は受講対象外」と明記。事業所所属要件あり。 個人単独申込不可(要項PDFより)。 | 奈良県庁 |
| 和歌山県 | × | 研修申込は障がい福祉サービス事業所を対象。 個人単独申込は不可。 新規開設予定の事業所名を記載すれば受付可能(要項参照)。 | 和歌山県庁 |
| 鳥取県 | × | 県内障がい福祉サービス事業所に勤務・従事予定の方が対象。 個人単独での申込み不可(要項・サイト記載)。 ただし事業所として開設予定の場合は申込可。 | 鳥取県庁 |
| 島根県 | × | 電子申請や福祉人材センター経由の申込フォームはあるが、「申し込みは県内事業所等に限る」と要項に明記。 個人単独申し込みは不可(要項PDFより)。 | 島根県庁 |
| 岡山県 | × | 障がい福祉サービス事業所等に従事する予定の方が対象。 申込には「所属長の推薦・押印」が必須。 個人単独申し込み不可(要項PDFより)。 | 岡山県庁 |
| 広島県 | × | 研修申込みは法人単位。 要項に「個人からの申込みは受付できません」と明記。 推薦法人が責任を負う制度設計(要項PDFより)。 | 広島県庁 |
| 山口県 | × | 電子申請対応。 山口県内在住者は「二次募集」、県外在住者は「追加募集」で個人申込可能(基礎研修)。法人推薦や事業所所属の必要なし。 ただし実務経験要件あり。 | 山口県庁 |
| 徳島県 | × | 「県外事業所所属者は受講不可」と明記あり。 県内指定事業所に従事予定の方が対象であり、個人単独での申し込みは不可と読み取れる内容(開催要項PDFより)。 | 徳島県庁 |
| 香川県 | × | 電子申請&実務経験調査書郵送が必要。 対象は「指定障がい福祉サービス事業所等において配置しようとする者」のみ。 個人単独での申し込み不可(要項より)。 | 香川県庁 |
| 愛媛県 | ◯ | 愛媛県外・事業所未所属でも申込可能と公式ページ(県サイト)および実施機関の要項PDFに明記。 ・県サイト →「愛媛県外の方も申込み可能」 ・愛媛県社会福祉士会 要項PDF →「所属がない場合、以前所属していた事業所名でも可」「定員超過時は県内優先」と記載あり。 | 愛媛県庁 |
| 高知県 | × | 「現に従事していることが必要」と要項に明記あり。 事業所等での現勤務が前提であり、個人単独での申込は不可と判断される内容。 | 高知県庁 |
| 福岡県 | × | 基礎研修申し込みは「法人推薦書+実務経験証明書の提出が必須」で、県・社福士会の要項により個人単独での申し込みは不可と明記。 県外申込みは実績により制限あり。 | 福岡県庁 |
| 佐賀県 | × | 要項に「一事業所1名・一法人2名以内」「実務経験証明書必須」と明記あり。 事業所単位での受講者制限が設けられており、個人単独での申し込みは制度上不可と判断できる。 | 佐賀県庁 |
| 長崎県 | × | 申込書に法人情報の記載欄あり。 実務経験証明書・勤務体制表の提出が必要であり、申込者に法人所属が求められる内容。 個人単独での申込は制度的に不可と判断できる | 長崎県庁 |
熊本県 | × | 募集要項に「事業所に従事中・従事予定者対象」「勤務先情報・法人担当者欄・実務経験証明書必須」と明記あり。 申込書のフォーマット自体が法人所属者前提で設計されており、個人単独申し込みは制度上不可と判断できる。 | 熊本県庁 |
大分県 | × | 法人からの推薦書と実務経験証明書の提出が必須。 申込フォームには「法人推薦が必要」と明記あり。 提出書類に勤務先情報・勤務体制も含まれるため、事業所所属が前提であり、個人単独申し込みは不可(要項・申込画面より)。 | 大分県庁 |
宮崎県 | × | 指定障がい福祉サービス事業所への配置予定者が対象と要領に明記。 Web申込+要項PDFには勤務先所属が前提で設計されており、個人名義の単独申し込みは制度上不可(宮崎県研修実施要領より)。 | 宮崎県庁 |
| 鹿児島県 | × | 申込は「事業所登録からに限る」と要項に明記されており、個人登録からの申し込みは受付不可。 実務経験証明書や勤務体制表の提出が必要なため、事業所所属が前提で、個人単独申し込みは制度上不可(申込システムより) | 鹿児島県庁 |
| 沖縄県 | × | 沖縄県では原則「法人推薦が必要」で、個人申込枠もあるが、法人推薦が得られない理由を申請書に記載する必要あり。 勤務先・実務要件・法人情報の記入欄があるため、実態として個人単独申込は制度上限定的(申込書・要項より)。 | 沖縄県庁 |
上記につきましては、あくまで弊社調べのまとめ情報となります。
正確な情報は対象の自治体にお問い合わせください。
サビ管・児発管研修個人で申し込み方法について
サビ管・児発管研修に個人で申し込むには、事前にいくつかの確認や準備が必要です。
ここでは、基本的な申し込み手順を3つのステップで解説します。
【STEP1】研修事業所・自治体の募集要項を確認
公式サイト等で「個人申込可否」「申込期間」「必要書類」を確認します。
自治体によって、先着順で受付を行う場所もあるため、注意が必要です。
【STEP2】必要書類の準備
サビ管・児発管研修の申し込みに必要な書類等を確認し、申し込みの準備を行います。
提出書類は自治体や研修ないようによって若干異なる場合もありますが、一般的には以下のような書類が必要です。
- 実務経験証明書
- 推薦状(不要な場合もあり)
- 申込書
- その他、身分証明書や資格証など
準備が整ったら指定の申し込み方法に従い、申し込みを行います。
【STEP3】指定の申込方法で申請
研修の申し込み方法も自治体によって異なります。主な申し込み方法は以下の通りです。
- Web申込フォーム
- 郵送
- 事業所経由申込(必須の場合のみ)
郵送先に関しては、事業所の所在地によって郵送先が異なる場合があるため、必ずお住まいの自治体の申し込み要項をチェックしましょう。
地元自治体で個人申し込みが難しい場合代替案
オンライン研修を活用する
地元の自治体でサビ管・児発管研修に申し込みを行いたいが、希望者多数で受講が難しい場合は、他県からの申し込みも受け付けている自治体から申し込みを行うのも一つの手段です。
ほとんどの場合、「県内の事業所に従事する者(または予定者)」が最優先されます。
県外からの申込みは、定員に空きが出た場合に限られている場合が大半です。
また、県外からの申込みが可能でも、「その県で就労する予定があること」が条件となっている場合があります。
募集要項を詳細に確認する必要があります。
県外の研修に参加できた場合でも、演習(グループワーク)が集合研修の場合などは、県内での研修になるケースが多いため、他県で受講する場合、現地での集合研修の有無も事前に確認しておくことをお勧めします。
「資格取得支援制度」ある事業所へ転職を検討する
「資格取得制度」とは、福祉事業所が自社職員に対し、専門資格の取得をサポートする取り組みです。
サビ管・児発管資格についても、受講料補助・書類準備支援・業務調整など、制度を整備している法人が増えています。
たとえば、以下のような内容が挙げられます。
- 研修受講料の一部または全額を補助
- 実務経験証明や申込手続きを法人がサポート
- 研修受講中の勤務シフトや業務調整の配慮
資格取得支援を積極的に行っている事業所では、法人側で申し込みから受講までのフローを一括でサポートしてくれるため、
「制度がよくわからない」「個人で動けない」という方でも、安心してチャレンジできます。
また、研修を通じて将来的に管理者ポジションを目指すことができるため、キャリアアップの近道としても有効です。
「今すぐは難しい」と諦める前に、資格取得支援に積極的な事業所への転職という選択肢も、ぜひ視野に入れてみてください。
まとめ
サビ管・児発管研修は、以前よりも個人申し込みの門戸が広がってきています。
ただし、地域や研修事業者によって申込条件が異なるため、最新情報を必ず確認してください。
また、地元での受講が難しい場合は、オンライン研修や転職を通じたキャリアアップも視野に入れることをおすすめします。
サビ管・児発管としてキャリアアップを目指す方には、 転職支援サービス「ケア人材バンク」がおすすめです。
また、ケア人材バンクでは他にも、サビ管、児発管向けの役立つ記事を多数掲載しているほか、転職支援サービスも行っています。
完全無料で転職サービスを受けることができますので、ぜひご登録のうえ転職エージェントにご相談ください。
よくある質問FAQ
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 研修に関するFAQ
Q. サービス管理責任者(サビ管)や児童発達支援管理責任者(児発管)の研修は、個人で申し込めますか?
A. はい、可能です。以前は事業所経由での申し込みが一般的でしたが、近年はオンライン研修の普及もあり、個人での申し込みを受け付ける自治体や研修事業者が増えています。ただし、申し込みの可否や要件は自治体によって大きく異なるため、事前の確認が必須です。
Q. 研修に個人で申し込むには、どうすればよいですか?
A. まず、受講を希望する自治体や研修事業者の公式サイトで最新の募集要項を確認します。その後、必要な書類(実務経験証明書など)を準備し、指定された方法(オンラインフォーム、郵送など)で期間内に申請手続きを行います。
Q. 地元の自治体では個人申し込みができない場合、どうすればいいですか?
A. いくつかの代替案があります。まず、全国を対象としたオンライン研修を探す方法があります。また、将来的に転職を考えている場合は、「資格取得支援制度」を設けている事業所を探し、そこで働きながら研修を受けるという選択肢もあります。
Q. 個人で申し込む際の注意点はありますか?
A. 最も重要な点は、自治体や研修事業者ごとに申込要件、必要書類、申込期間が大きく異なるため、必ず公式サイトで最新かつ正確な情報を確認することです。依然として事業所の推薦状や証明が必要な場合もあるため、募集要項を隅々まで確認してください。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。